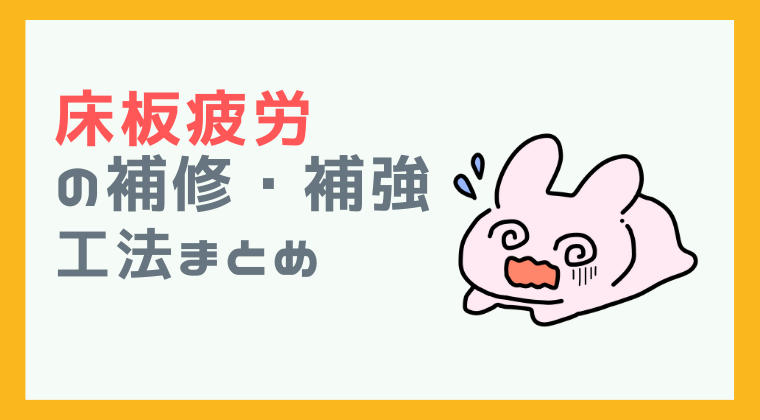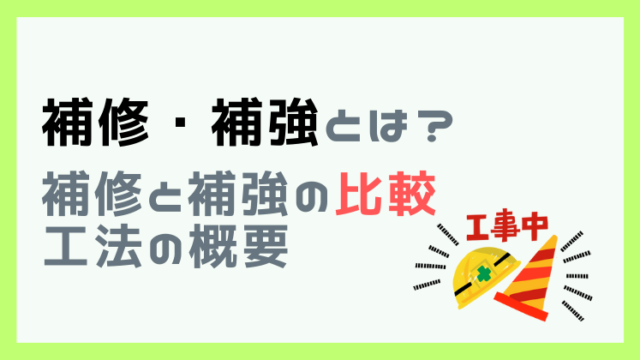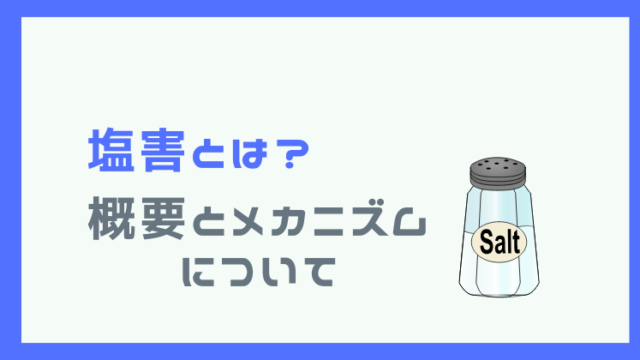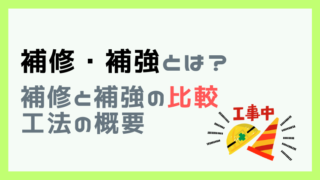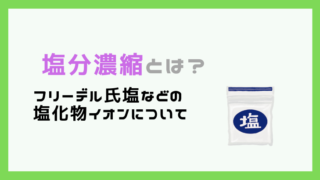こんにちは!
今回は床板疲労の補修・補強工法についてまとめてみます。
最後に問題もあるので、良ければ解いてみてください。
それではいってみましょう!
床板疲労の劣化過程と変状
まず、疲労により劣化した構造物の状態と、外観上のグレードについては次の通りです。
状態Ⅰ(潜伏期):主桁に沿った一方向ひびわれが数本確認できる程度の段階。主桁の拘束条件によっては乾燥収縮などによる橋軸直角方向のひびわれが進行する場合がある。
状態Ⅱ(進展期):主桁作用による主筋に沿った曲げひびわれが進展するとともに、配力筋に沿ったひびわれも伸展し始め、格子状のひびわれ網が形成される段階。外観上のひびわれ密度の増加は著しいが、床板の連続性は失われていない。
状態Ⅲ(加速期):ひびわれの細網化が進み、ひびわれ開閉やひびわれ面のこすり合わせが始まる段階。ひびわれのスリット化や角落ちが生じるとコンクリート断面の抵抗は期待できないので、床板の押し抜きせん断耐力は急激に低下し始める。
状態Ⅳ(劣化期):床板のひびわれが貫通して床板の連続性が失われ、貫通ひびわれで区切られたはり状部材となる段階。雨水の浸透や鉄筋腐食などに配慮する必要がある。
床板は橋軸方向に配置される鉄筋を配力筋、橋軸直角方向を主鉄筋として設計されます。
また、床板の劣化指標としては、次のものがあります。
潜伏期、進展期:ひびわれの方向、密度
加速期、劣化期:ひびわれ幅、たわみ
潜伏期:一方向ひびわれ
進展期:二方向ひびわれ
加速期:ひびわれの網細化と角落ち
劣化期:床板の陥没
補修・補強工法
次に、床板疲労の各劣化段階において適用できる補修・補強工法については次の通りです。
潜伏期:下面のひびわれに対して、必要に応じて鉄筋腐食の抑制対策をとる。表面被覆工法が有効。
進展期:水の存在で疲労の進展が速くなるので、漏水防止対策が重要。床板防水工法が有効。
加速期:ひびわれの密度増大やスリット化に伴い補修とともに補強が必要となる段階。増厚工法(曲げ補強として下面)、押し抜きせん断補強(上面または下面)が有効。また、コンクリート塊の抜け落ち等の第三者への影響を未然に防止する対策をとる。
劣化期:加速期と同様の対策をとる。
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
次の記述が適当か、不適当か選択してください。
「状態Ⅱ(進展期)は二方向ひびわれで、設計時に想定している二方向版としての機能(床板の連続性)が失われていると判断した。」
答えは下にスクロールしてください。

正解は不適当です。
曲げひびわれが進行して、二方向のひびわれに進展します。ひびわれの密度が大きくなっても、鉄筋コンクリート床板の連続性は失われず、耐荷力は特に問題となりません。
それでは、今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。