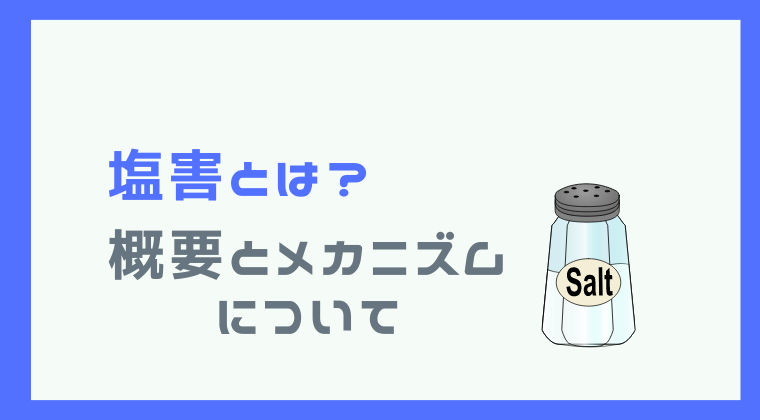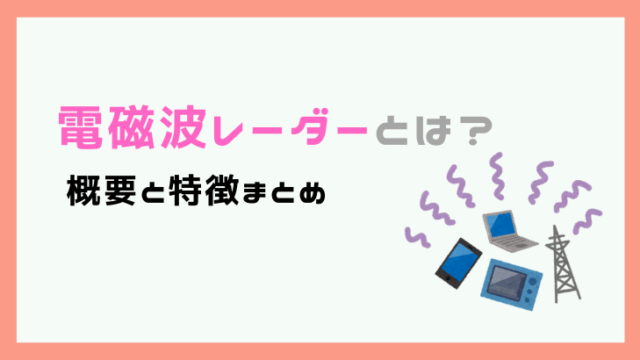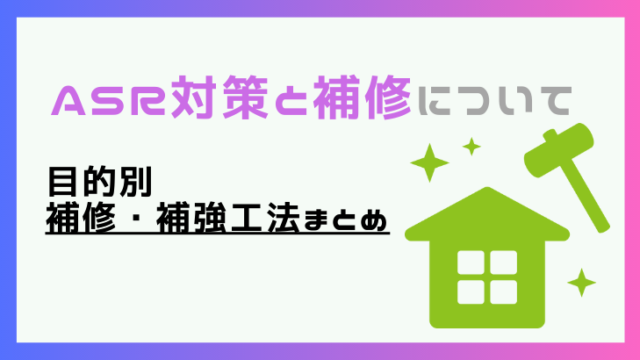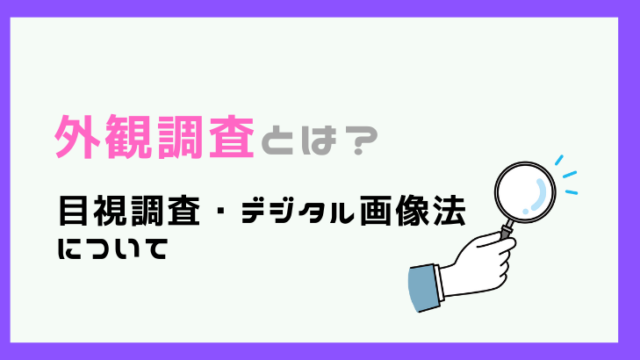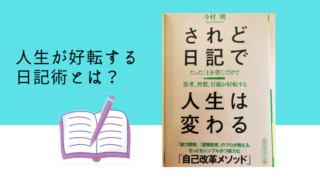今回は塩害の概要とメカニズム、防止対策についてまとめてみます。
最後に問題もあるので、お付き合いいただければ幸いです。
塩害とは?
塩害とは、塩化物イオンによりコンクリート中の鋼材が腐食することに伴い、腐食生成物の膨張圧でかぶりコンクリートにひびわれや剝離を引き起こしたり、鋼材の断面減少で部材の力学性能を低減させたりする現象のことです。
メカニズム
塩害のメカニズムは、おおむね以下のように説明されています。
- コンクリート内部は一般にpHが12以上の高アルカリです。鋼材は、高アルカリ環境下で表面に不動態皮膜を形成し、腐食しにくい状態におかれています。
- ところが、塩化物イオンが腐食発生に必要な濃度に達すると不動態皮膜が破壊されます。ここで、鋼材の腐食開始時期は、鉄筋位置の塩化物イオン濃度で判定します。通常、腐食発生限界塩化物イオン濃度は1.2kg/㎥が目安になります。
- 不動態皮膜が破壊されると、鉄イオンが細孔溶液中に溶け出すアノード反応と、電子がコンクリート中の酸素および水と反応して水酸化イオンを生成するカソード反応が起きます。
- この反応で生成した鉄イオンと水酸化イオンが反応して水酸化第一鉄を生成します。これによりアノード部で腐食が始まります。
- 腐食が進むと、鋼材は2~4倍の体積膨張を起こすため、その膨張圧力でコンクリートにひびわれ、剝離・剝落の損傷が生じ、これによって鉄筋腐食が促進されます。
- 塩害による鋼材腐食は、中性化による全面腐食とは異なり、マクロセル腐食のように局部的に激しく腐食する部分が形成される場合や、腐食の進行が速い場合が多いです。
防止対策
塩害の対策としては、次のことが有効です。
配合:コンクリート内部への塩化物イオン浸透を抑制するために、水セメント比を小さくして密実性を増加させる
設計:腐食発生限界濃度以上の塩化物イオンが鉄筋位置まで浸透しないように適切なかぶりを確保する
施工:スペーサーを用いるなど、所定のかぶりを確保するための管理を十分に行うとともに、適切な養生を実施する。また、干満帯には打ち継ぎ目を設けない
鉄筋:エポキシ樹脂塗装鉄筋やステンレス筋などの防食鉄筋を設ける
防錆剤:亜硝酸リチウムを含浸させ、腐食発生限界濃度を増加させる
予防保全:表面被覆工法や表面含浸工法を、新設あるいは短い供用期間の構造物に適用し、外部環境からの塩化物イオンの浸透を抑制する
塩害によって一旦ひびわれが発生すると、急激に進行する可能性が高いことから、初期の段階で適切な防止対策を実施するのが重要です。
問題
それでは最後に○×問題を解いてみましょう。
「内部の鉄筋が塩害で腐食していても外観上コンクリートに劣化が見られない場合、表面被覆工法を適用すれば劣化が防止できる」
○か×か。
答えは下にスクロールしてください。

正解は×です。
外観に変状がなくても鉄筋が腐食している場合には、コンクリート中の塩化物イオン濃度が高い可能性があるため、塩化物イオン濃度を測定し、その程度に応じた工法選定を行うことが必要です。
今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。