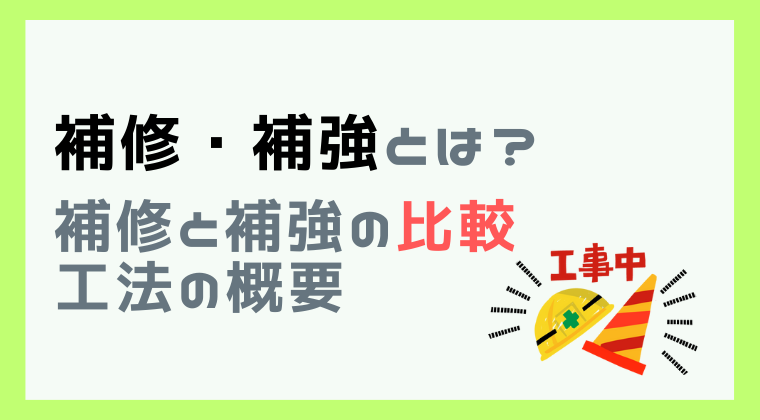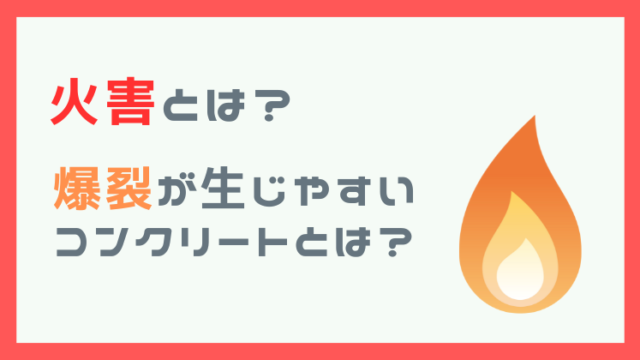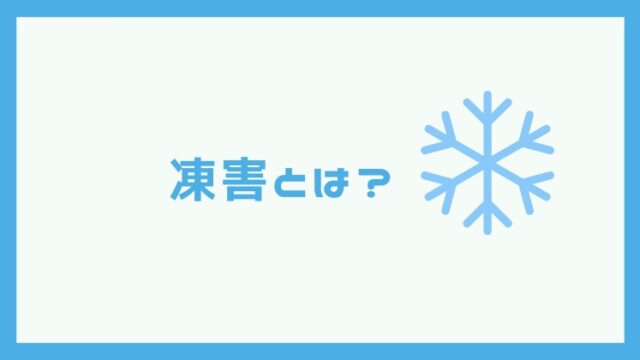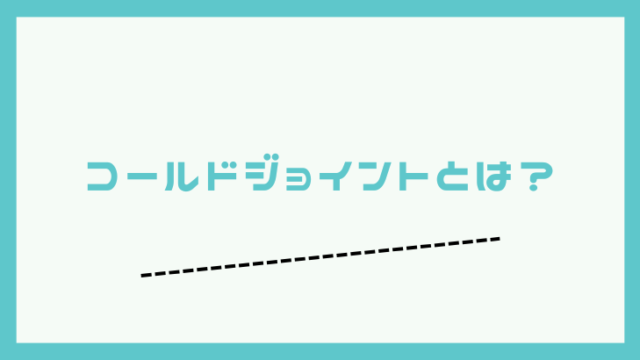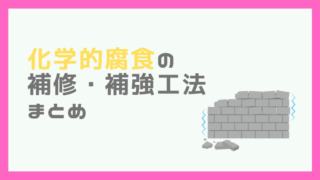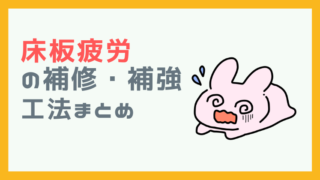こんにちは!
今回は補修と補強の違いと、工法の概要についてまとめてみます。
最後に問題もあるので、良ければ解いてみてください。
それではいってみましょう!
補修と補強の違い
補修・補強とは、構造物を診断し補修あるいは補強を必要と判断された場合にその状況に合わせて、構造物に求められる性能を回復するための対策のことです。
また、補修と補強の定義については次の通りです。
補修:劣化した部材や構造物の今後の劣化進行を抑制し、耐久性の回復・向上と第三者影響度の除去、低減を目的とする対策。耐荷性あるいは力学的な性能の回復・向上は目的としない。
補強:部材や構造物の耐力や剛性などの力学的な性能低下を回復または向上させることを目的とする対策。
比較すると、次のようになります。
| 項目 | 補修 | 補強 |
| 目的 | 耐久性の回復、向上 | 力学的性能の回復、向上 |
| 要求性能 | 耐久性能、美観・景観、使用性能の一部 | 安全性能、使用性能の一部 |
| 材料 | セメント系材料、樹脂系材料 |
セメント系材料、樹脂系材料、鋼板、連続性繊維補強材、PC鋼材、鉄筋 |
補修工法
補修工法の概要
補修工法は主に次のようなものがあります。
・ひびわれ補修工法(ひびわれ被覆工法、注入工法、充填工法)
・断面修復工法
・表面保護工法(表面被覆工法、含浸材塗布工法、はく落防止工法)
・電気防食工法
・電気化学的補修工法(再アルカリ化工法、脱塩工法、電着工法)
補修工法の選定
補修工法選定では、劣化の種類および現状、劣化の進行過程、要求性能などを明確にし、次の項目を考慮して決めます。
- 維持管理の区分、補修後の点検方法、頻度など
- 構造物の重要性
- 残存供用期間(補修後の構造物に期待される耐用期間)
- 経済性
各工法の適用目的
各工法の適用目的については、ざっくりとですが以下の通りです。
○ひびわれ補修工法:ひびわれを閉塞して機能回復、あるいは劣化要因の浸入を抑制する。
○断面修復工法:劣化要因を除去し、断面を復旧する。
○表面保護工法
・表面被覆工法:劣化要因の浸入を抑制する。
・含浸材塗布工法:劣化に対する抵抗性を増大する。
・はく落防止工法:仕上げ材など表層のはく落を防止する。
○電気防食工法:鉄筋の腐食を抑制する。
○電気化学的補修工法
・再アルカリ化工法:鉄筋の腐食を抑制する。
・脱塩工法:鉄筋の腐食を抑制する。
・電着工法:劣化要因の浸入を抑制する。
補強工法
補強工法の概要
次に、補強工法は主に次のようなものがあります。
・コンクリートの断面増加(増厚工法、RC巻立て工法)
・補強材の追加(接着工法、巻立て工法)
・プレストレスの導入(外ケーブル工法)
・部材の追加(縦桁増設工法)
・支点の追加(支持工法)
・コンクリート部材の交換(打替え・取替え)
補強工法の選定
補強工法の選定は、次のような流れで検討されます。
- 変状原因の検討
- 補強方法の決定
- 目標性能の設定
- 補強方法の選定
- 部材の補強設計
- 補強後の全体構造の性能評価
- 判定
- 補強工事
(以前、過去問で補強工法選定の順番に関する問題を見た覚えがあります。目を通しておくと安心かもしれません。)
各工法の適用目的
各補強工法の適用目的については、またざっくりとですが以下の通りです。
増厚工法:スラブの曲げ・せん断補強、スラブおよびはりの振動対策
巻立て工法:柱の軸力・せん断補強、じん性改善、曲げ補強
接着工法:主としてスラブおよびはりの曲げ・せん断補強
外ケーブル工法:主としてはりの曲げ・せん断補強
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
鉄筋コンクリート単純桁橋の変状に対して実施した対策に関する次の記述は、適当か不適当か選択してください。
「振動障害が生じていたので、桁および床板のひびわれにエポキシ樹脂を注入した。」
適当か不適当か。
答えは下にスクロールしてください。
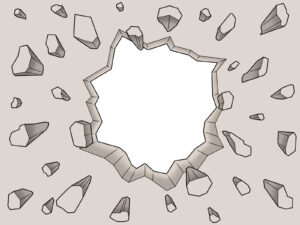
正解は、不適当です。
ひびわれに樹脂を注入しても剛性は増加しないため、振動障害に対する対策としては不適当です。
今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。