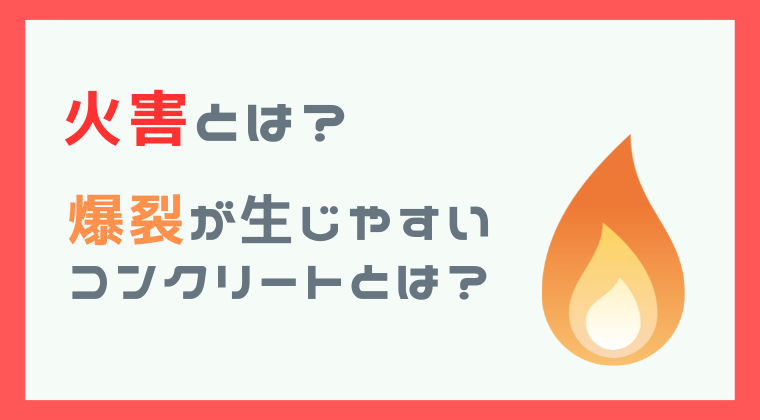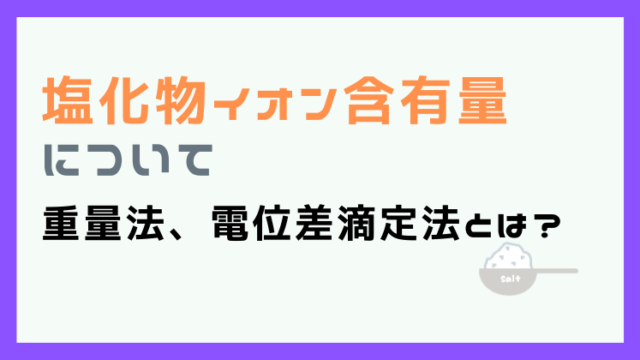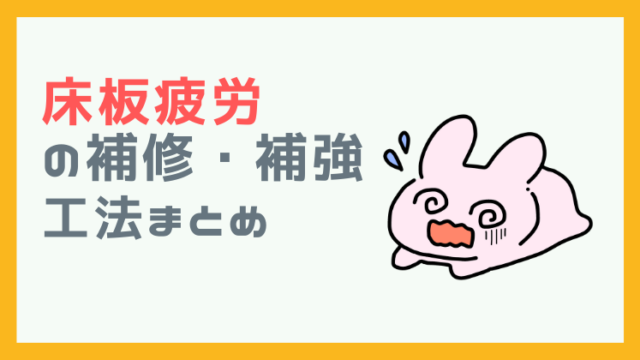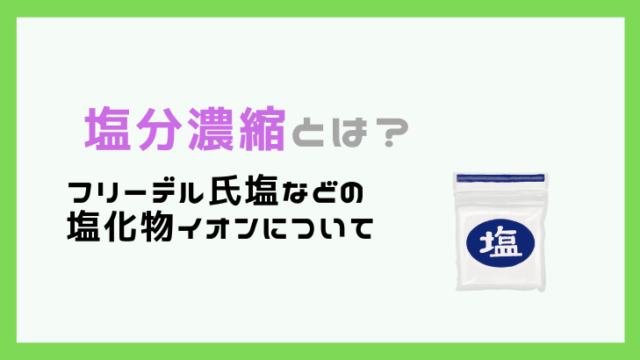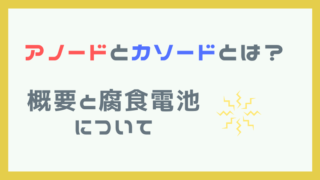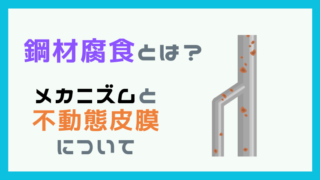今回は、火害についてまとめてみようと思います。
良ければ最後までお付き合いください。
火害とは?
概要
コンクリートが火熱によって受ける損傷を火害といいます。
コンクリートは、火害によって外観的、化学的、物理的に変状をきたします。
火害は他の劣化のように、経年的な性能低下を示す変状ではありません。
メカニズム
セメントペースト部は600℃までは収縮しますが、骨材は膨張します。
また、コンクリート中の自由水が加熱されて膨張します。
セメントペーストと骨材の熱膨張係数の差、コンクリート中の水の膨張により、内部応力が増大し、内部組織が破壊されます。
これらのことから、表層部で爆裂を起こしたり、ひび割れが生じ、剥落する場合もあります。
爆裂は、コンクリートが高強度化され組織が緻密になるほど生じやすくなります。
具体的には、次のようなものです。
・水セメント比の低い緻密なコンクリート(透気係数が小さく、水蒸気が解放されにくい)
・含水率の高いコンクリート(水が多く、水蒸気圧が大きくなる)
受熱温度
火害を受けたコンクリートが到達した最高の温度のことを受熱温度といいます。
コンクリートの変色状況と受熱温度の関係は次の通りです。
~300℃ すすの付着
300~600℃ ピンク色
600~950℃ 灰白色
950~1200℃ 淡黄色
1200℃~ 溶融
弾性係数と強度について
水酸化カルシウム(Ca(OH)₂)は500~580℃の加熱でCa(OH)₂→CaO₊H₂Oに熱分解し、pHの低下が起こります。ケイ酸カルシウム水和物(C-S-H)は600~700℃で熱分解します。
100℃以上では、遊離水・結晶水の一部が分離・消失します。
300℃までは強度の低下はほとんどありません。
500℃を超えると50%以下となりますが、時間とともに回復し、1年で85%以上回復します。
しかし、弾性係数は大幅に低下し、500℃で1年経過後でも50%以下と圧縮強度とは異なります。
鉄筋について
引張強度は300℃を超えると大きく低下し、500℃で1/2となります。
降伏点は加熱温度が高くなるにつれて低下します。
500℃以上の加熱を受けると強度および降伏点は回復しないため、500℃が鉄筋の安全限界温度と考えられています。
調査方法
外観調査では、コンクリート表面の色などを調査することでおおよその受熱温度を推定するとともに、中性化深さ、リバウンドハンマーなどにより表面強度、コアによる強度、ヤング係数、鉄筋の強度などを調査します。
機器を使用する調査方法としては、粉末X線回析、示差熱分析、UVスペクトル法などがあり、それぞれCa(OH)₂の定量、ナフタレイン系やリグニンスルホン酸系混和剤による受熱温度の推定ができます。
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
火災を受けたコンクリートに関する次の記述は適当でしょうか、不適当でしょうか。
「火災によってコンクリートのアルカリ性が低下する原因は、水酸化カルシウムの熱分解である」
適当か、不適当か。
答えは下にスクロールしてください。
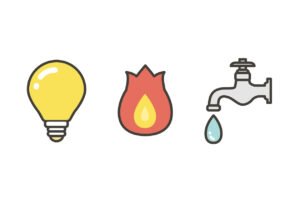
正解は、適当です。
コンクリートは500~580℃に加熱されると、水酸化カルシウム(Ca(OH)₂)が分解してアルカリ性が失われます。このため、フェノールフタレイン法による中性化試験を行い、健全部と比較することによって、受熱温度を推定することができます。
それでは、今回は以上になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。