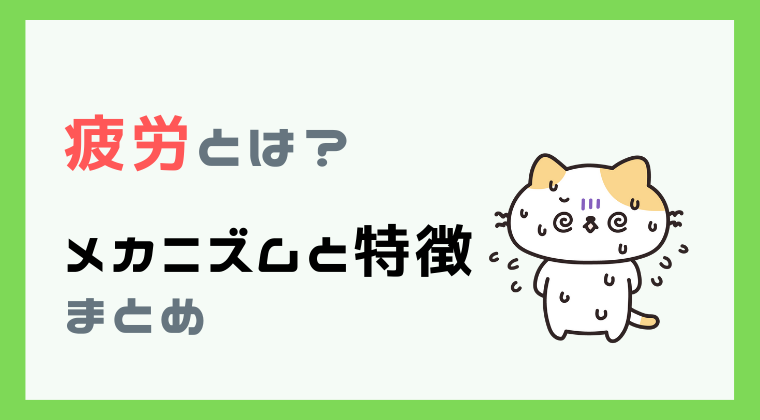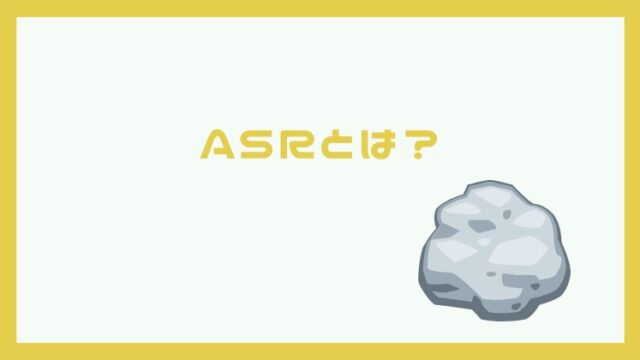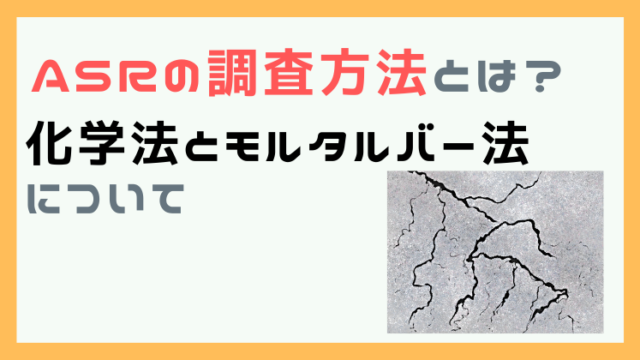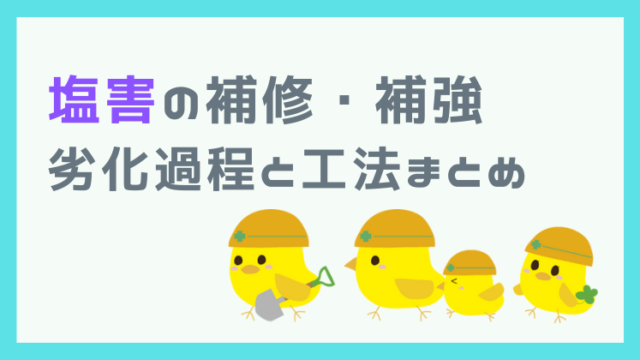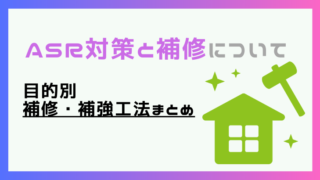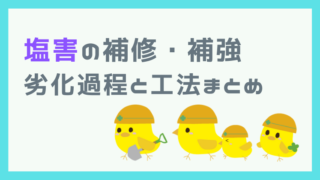こんにちは!
今回は疲労についてまとめてみます。
最後に問題もあるので、良ければ解いてみてください。
それではいってみましょう!
疲労とは?
コンクリート部材に作用する応力が静的強度に比較して小さいレベルの荷重作用を繰り返し受けることにより、脆性的に破壊に至る現象を疲労、または疲労破壊といいます。
疲労が問題となるのは、構造物に繰り返し荷重が作用する道路や鉄道構造物、海洋構造物などです。対象となる部材はスラブやはり等があります。
メカニズム
鋼材の劣化メカニズム
鋼材の劣化のメカニズムは、次の通りです。
- 応力集中部で金属の結晶レベルでのすべりが生じ、それが初期ひびわれと呼ばれる観察可能な大きさに発達する。
- その後、疲労ひびわれが伝搬する進展期を経て、破面にへき開などが認められる破断に至る。
応力振幅が大きい場合は、疲労寿命に対する進展期の割合が多くなりますが、応力振幅が小さい場合は潜伏期の割合が卓越し、大部分がひびわれ発生に要した繰り返し回数となります。
さらに、次のような特徴があります。
鉄筋径が大きいほど疲労寿命は小さくなる。
曲げ加工部、溶接部は、残留応力や応力集中の影響を受け疲労強度が低下する。
鉄筋が腐食すると断面欠損とともに、断面が不均一となり応力集中が生じて疲労強度は低下する。
コンクリート床板の劣化メカニズム
コンクリート床板のメカニズムは次の通りです。
- 床板の橋軸方向の収縮が主桁などに拘束され、橋軸直角方向(主鉄筋方向)に収縮ひびわれが発生する
- 橋軸直角方向に分配される荷重が増大し、橋軸方向(配力鉄筋方向)にもひびわれが発生する
- 繰り返し載荷されることによって、橋軸直角方向のひびわれは網細化とひびわれスリット化・角落ちが生じる
- 橋軸直角方向のひびわれが貫通して、床板の連続性が失われ、貫通ひびわれで区切られたはり状部材となる
- 最終的には、これらの床板がせん断疲労破壊して、コンクリート塊が押し抜かれる
また、次のような特徴があります。
水中の疲労強度は気中に比べて小さくなる。
疲労による劣化は、雨水の浸透が多い部分で発生しやすい。
床板厚さが大きい方が曲げひびわれが発生しにくく、床板の疲労強度は大きくなる。
配力筋が少ないと主筋方向(橋軸直角方向)の曲げひびわれが発生しやすく、床板の疲労強度が小さくなる。
交通量が多く、作用する荷重が大きい(大型車が多い)ほど疲労破壊しやすくなる。
劣化過程と損傷状況
疲労劣化は次のような段階で進行します。
潜伏期:軽微な変状や一方向ひびわれが見られるものの、十分に機能する状態
進展期:二方向ひびわれ、せん断・ねじりせん断に対する剛性が徐々に低下
加速期:亀甲状ひびわれ、耐荷力の急激な低下
劣化期:剝落・陥没、せん断強度の著しい低下、抜け落ち
劣化期において、せん断抵抗力の低下は、水が存在する場合に特に著しくなります。貫通ひびわれから浸透した雨水は、コンクリート中の石灰分を溶解し、遊離石灰が床板下面に沈着するようになります。また、浸透する水の影響によ鉄筋の腐食が著しくなり、鉄筋の錆汁も付着するようになります。
これらは縦・横断勾配が小さい箇所や、舗装の轍割れなど雨水の滞水しやすい箇所で顕著となります。
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
次の記述が適当か、不適当か選択してください。
「主鉄筋方向に加えて配力鉄筋方向にもひびわれが進展したので、床板の耐荷力は低下したと判断した」
答えは下にスクロールしてください。

正解は、不適当です。
主鉄筋方向と配力筋方向にひびわれが進展した段階では、鉄筋コンクリート床板の連続性は失われていないため、床板の耐荷力は低下していないと推測されます。
それでは、今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。