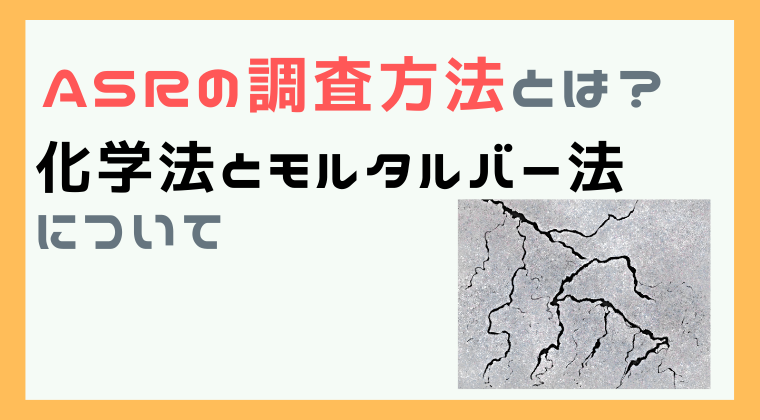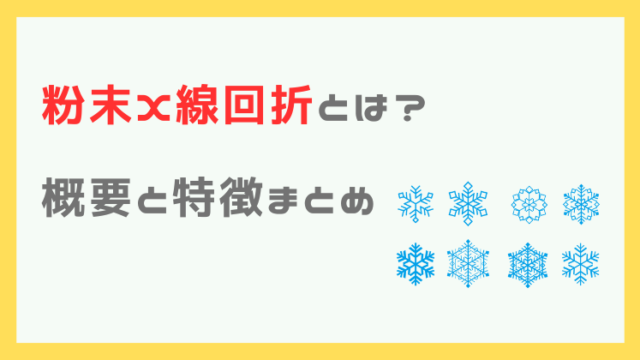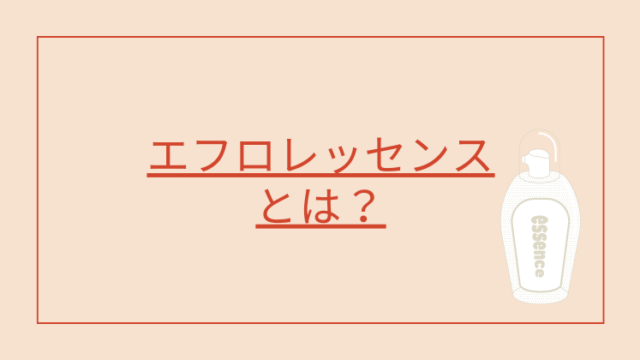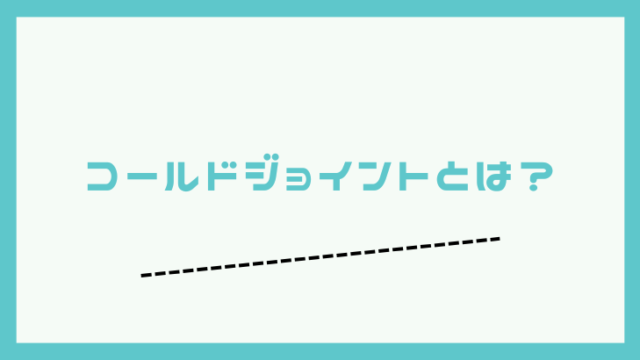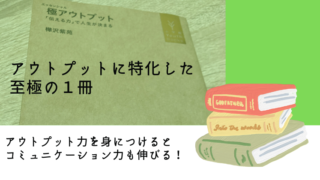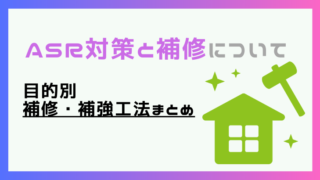こんにちは!
今回は、ASRの主な調査方法についてまとめてみようと思います。
最後に問題もあるので、解いてみてください。
それでは、良ければ最後までお付き合いください。
ASRのグレードと劣化状態
まず、ASRにより劣化した構造物の外観上のグレードと劣化状態についてです。
グレードは4段階に分かれており、それぞれ次のような特徴があります。
状態Ⅰ(潜伏期):ASRによる膨張およびそれに伴うひびわれがまだ発生せず、外観上の変化が見られない。
状態Ⅱ(進展期):水分とアルカリの供給下において膨張が継続的に進行し、ひびわれが発生し、変色、アルカリシリカゲルの滲出が見られる。しかし、鋼材腐食による錆汁は見られない。
状態Ⅲ(加速期):ASRによる膨張速度が最大を示す段階で、ひびわれが進展し、ひびわれ幅および密度が増大する。また、鋼材腐食による錆汁が見られる場合もある。
状態Ⅳ(劣化期):ひびわれ幅、密度がさらに増大し、段差、ずれや、かぶりの部分的な剝離・剝落が発生する。鋼材腐食が進展し錆汁が見られる。外力の影響によるひびわれや鋼材の損傷が見られる場合もある。変位・変形が大きくなる。
骨材中の反応性鉱物
骨材中の反応性鉱物の調査方法として、偏光顕微鏡観察、SEM、X線回折があります。
促進膨張試験
促進膨張試験とは、アルカリシリカ反応が疑われるコンクリート構造物から採取したコア供試体を促進条件下に保管し、反応を促進させて、アルカリシリカ反応性の有無や最終的な膨張量を判定する試験のことです。
主に次の3つが挙げられます。
JCI-DD2法:温度40℃、湿度100%条件下にて養生します。判定基準は、阪神道路公団で全膨張量0.1%を超えるものを有害、建設省で促進養生13週後の膨張量が0.05%以上となるものを有害と判定します。
デンマーク法:温度50℃の飽和NaCl溶液中に浸漬し、3か月で0.1%未満は膨張性なしと判定します。
カナダ法:温度80℃の1N-NaOH溶液中浸漬により、14日間で0.1%以下は無害と判定します。
骨材のアルカリシリカ反応性試験
骨材のアルカリシリカ反応性試験については、骨材に付着したセメント水和物を塩酸により溶解して試料を採取します。主な方法は次の2つです。
化学法:粉砕した骨材試料を80℃の1N-NaOH中に24時間浸漬し、ろ液の溶解シリカ量とアルカリ濃度減少量から「無害」または「無害でない」かを判定します。
モルタルバー法:水酸化ナトリウムを添加して等価アルカリ量(1.2%)のモルタル供試体を、湿気箱(温度40℃、相対湿度100%)に保存し6ヶ月の膨張量を測定します。膨張量0.1%以上であれば「無害でない」と判定します。
アルカリシリカゲルの判定
アルカリシリカゲルの判定には、偏光顕微鏡観察、蛍光X線分析、SEM、酢酸ウラニル蛍光法などがあります。
アルカリ量の測定
アルカリ量の測定では、コンクリート試料を粉砕した微粉末試料やコア試料により、コンクリート中のアルカリを採取してアルカリ量を測定し、診断の材料とします。主に次の2つの方法があります。
微粉末試料による分析:コンクリート試料を微粉末して調整し、強酸処理や熱水抽出によって抽出したアルカリを含む水溶液サンプルを、吸光光度計を使用し含有量を測定します。
コア試料による分析:コンクリートコアを密封容器内で加圧し採取された細孔溶液のOH⁻、Na⁺、K⁺を測定します。
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
次の記述は適当か、不適当か選択してください。
「ある構造物について、採取コアによる強度試験で、圧縮強度の低下は認められなかったため、ASRによる劣化進行の可能性が低いと判断した」
正解は下にスクロールしてください。
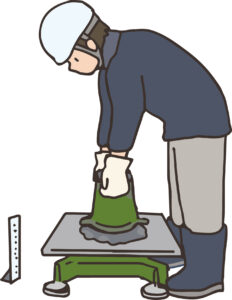
正解は、不適当です。
圧縮強度試験のみで、ASRによる劣化進行の可能性を判断することは不適当です。
それでは、今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。