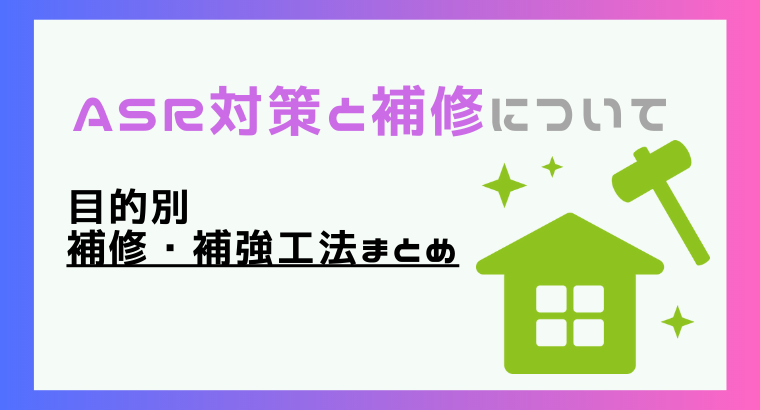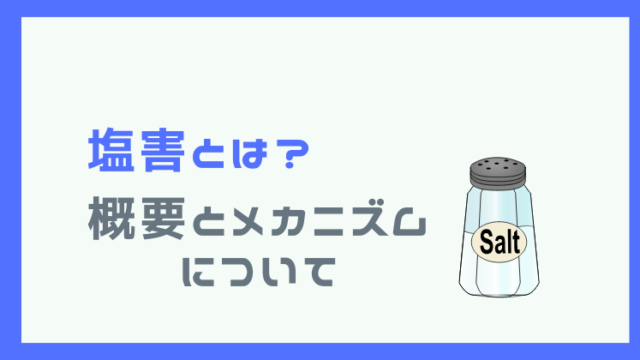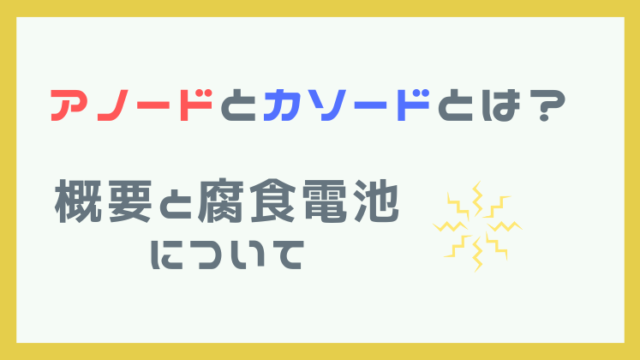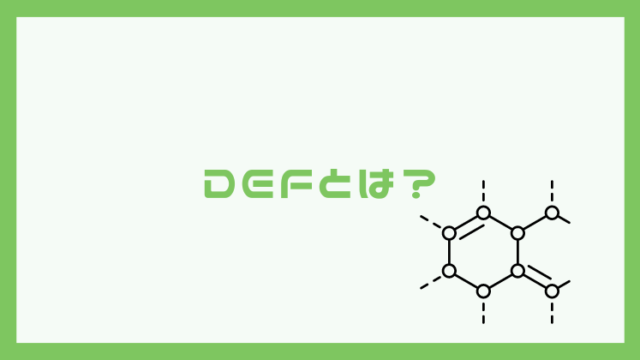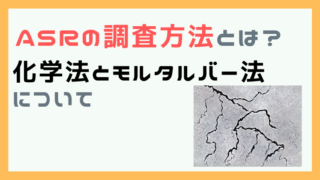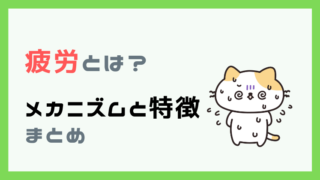こんにちは!
今回はASR対策についてまとめてみます。
最後に問題もあるので、良ければ解いてみてください。
それではいってみましょう!
ASRの目安
まず、ASRであると判断するための特徴についてまとめてみます。
骨材のアルカリシリカ反応性:化学法またはモルタルバー法によって無害でないと判定された場合で、無害と判定されても反応する場合があります。
アルカリシリカゲルの有無:骨材の周囲およびその周辺にアルカリシリカゲルの生成が認められる場合。
強度および弾性係数など:強度および弾性係数の低下が認められ、しかも弾性係数の低下が強度の低下より著しい場合。
構造物コンクリートの残存膨張量:構造物から採取したコアを用いた促進膨張試験の結果、有意な残存膨張が認められる場合。反応が収束した構造物のコアは残存膨張を示さないことに注意が必要です。
また、ASRによる劣化の兆候は、ひびわれ、変位・変形、段差、変色、ゲルの滲出、ポップアウトなどがあります。
目視観察のみではASRであると判断できない場合があるため、ASRが予想される場合には、日射、水分、海水、凍結防止剤などの影響を受けやすい箇所を重点的に点検することが重要です。
ASRの対策
それでは、ASRの対策についてです。
ASRによる劣化は、次の3つの条件下において進展します。
- 限界値以上のアルカリの存在
- 限界値以上の反応性シリカ量の存在
- 十分な水分の供給
したがって、ASRを抑制するには、これらの必要3条件のうち1つ以上を取り除くことが基本となります。
また、新設構造物に対するASRの抑制対策としては、次の4つが挙げられます。
コンクリート中のアルカリ総量の抑制
抑制効果のある混合セメント等の使用
安全と認められる骨材の使用
撥水剤などの表面塗布
ASRの補修
次に、ASRの補修についてです。
対策にも書きましたが、ASRの補修においても水分の供給を断つことが基本となります。
目的に応じた補修・補強工法は次の通りです。
ASRの進行を抑制:表面処理(被覆、含浸)、ひびわれ注入、水処理
ASRの膨張を拘束:プレストレスの導入、銅板・PC・FRP巻立て
劣化部の除去:断面修復
鋼材の腐食抑制:ひびわれ注入、ひびわれ充填、表面処理(被覆、含浸)
第三者影響度の除外:はく落防止
耐荷力の回復・向上:銅板・FRP接着、プレストレスの導入、増厚、銅板・PC・FRP巻立て、外ケーブル
ASRによるコンクリートの膨張は、潜伏期、進展期、加速期、劣化期という過程をたどるため、補修の対象となる構造物がいずれの段階にあるかを判断することが、補修の工法・材料の選択において重要となります。
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
次の記述は適当か不適当か選択してください。
「コンクリート中のアルカリ分を減らすために、かぶり部分を除去してポリマーセメントモルタルにより断面修復した」
答えは下にスクロールしてください。

正解は、不適当です。
かぶり部分のコンクリート除去については、これによって内部コンクリート中のアルカリ量は減少せず、アルカリ骨材反応は抑制できないため、対策として不適当ということになります。
それでは、今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。