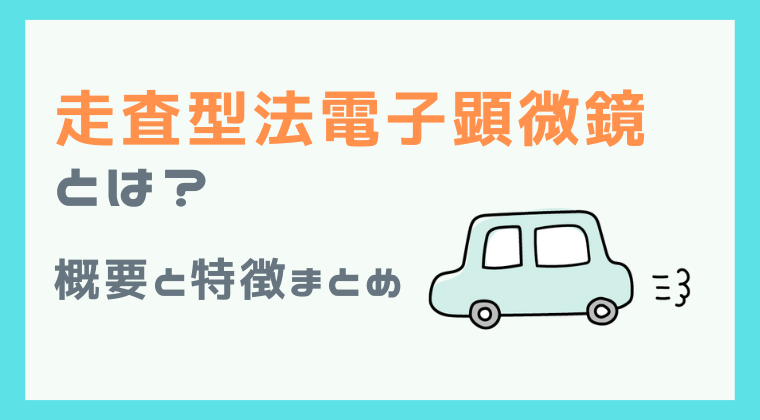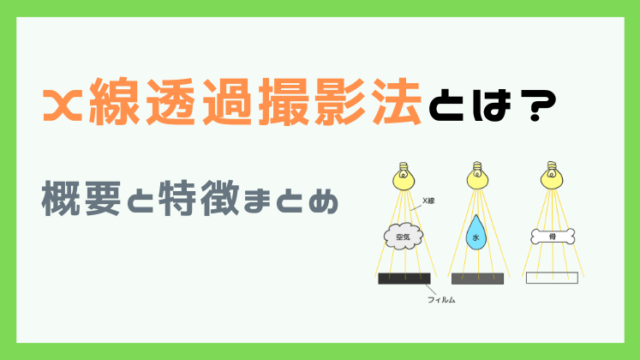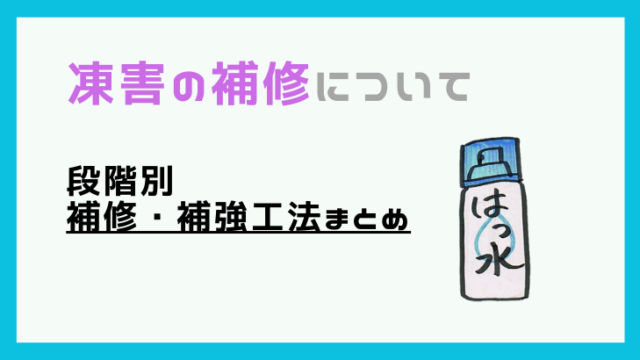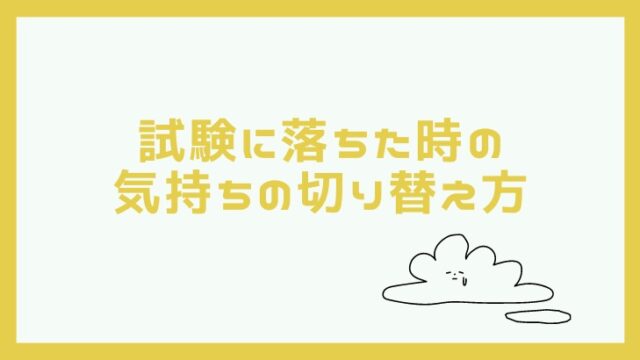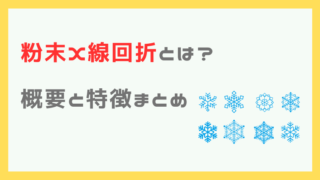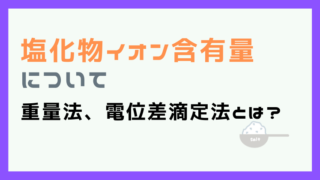こんにちは!
今回は走査型電子顕微鏡(SEM)についてまとめてみます。
最後に問題もあるので、良ければ解いてみてください。
それではいってみましょう!
走査型電子顕微鏡(SEM)とは?
走査型電子顕微鏡とは、二次電子、反射電子などの信号を検出し、電子線を当てた座標の情報と組み合わせることによって、像を構築し、画面上に試料表面の拡大像を表示する超高倍率の顕微鏡です。物質表面の陰影をとらえ、最高500万倍にまで対象を拡大することができます。
測定目的
物質の形態観察(低倍率)
結晶状態観察(高倍率)
測定方法
分析前の処理として炭素、金などの金属の蒸着を行います。
試料表面に電子ビームを照射すると、試料から二次電子が放出されます。
SEMは試料面上を走査しながら電子ビームを照射し、走査範囲全体から発生する二次電子を検出して、それを電気信号に変換してCRT上に映像化します。
顕微鏡像では、試料の凹凸がコントラストとして観察されます。
適用対象
無機物、有機物を問わずほとんどの物質を観察できます。具体的には以下のようなものがあります。
低倍率:空隙の形態・分布状況、アルカリシリカゲルの存在状態など
高倍率:骨材とセメントペーストの界面の状態、セメント硬化体の結晶(エトリンガイトなど)の生成状態など
水を含んでいるサンプルは装置に悪影響を及ぼしかねません。物質の特定は難しく、専門技術者の判断を仰ぐことが必要な場合もあります。
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
硬化コンクリートの調査に関する次の記述が、適当か不適当か選択してください。
「針状結晶の生成を、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて測定した」
答えは下にスクロールしてください。

正解は適当です。
走査型電子顕微鏡(SEM)は、顕微鏡の一種でセメント硬化体組織、アルカリシリカゲル、エトリンガイト(針状結晶)の生成状態を調査することができます。
それでは、今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。