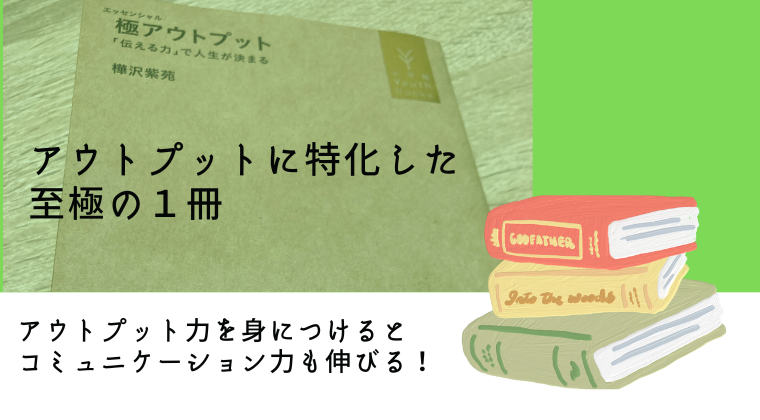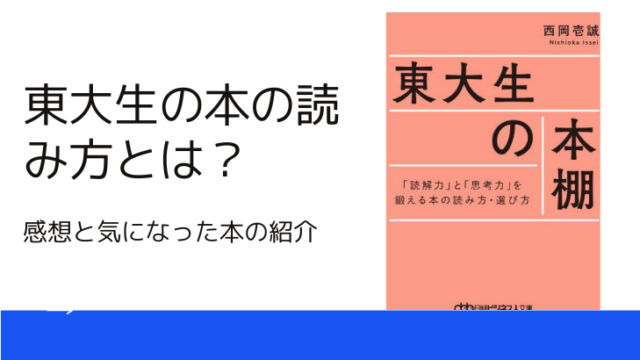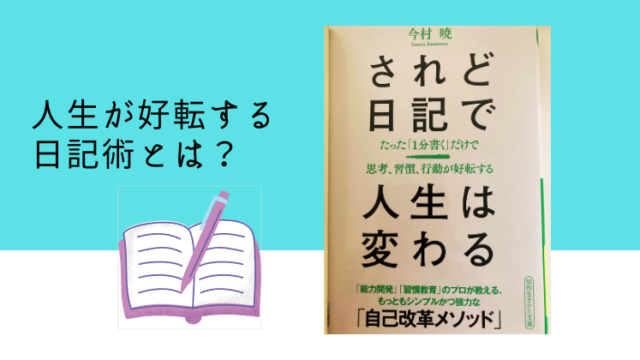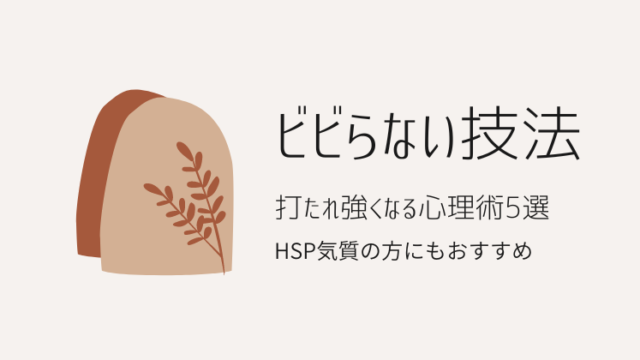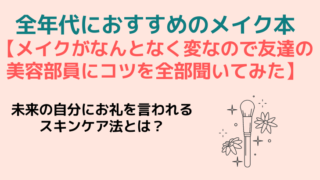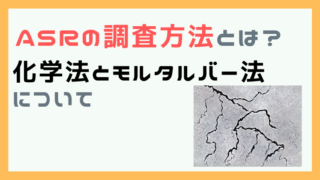こんにちは!
今回は、樺沢紫苑著「極アウトプット『伝える力』で人生が決まる」について要点と感想をまとめてみようと思います。
樺沢紫苑さんといえば、「アウトプット大全」や「神・時間術」が有名だと思います。
本屋さんで目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回ご紹介するのは、著者の代名詞とも言える「アウトプット」に特化した文庫本です。
この記事は、
アウトプットについて知りたい
アウトプットすることで得られる効果が知りたい
本の内容をざっくりと知りたい
このような方におすすめです。
本書は全5章で構成されており、
アウトプットって何だろう
コミュニケーション下手は克服できる
話す
書く
行動する
上記の順番でアウトプットについて掘り下げてあります。
それでは、私が重要だと感じたポイントを5つご紹介させてください。
 |
極アウトプット 「伝える力」で人生が決まる (小学館YouthBooks) [ 樺沢 紫苑 ] 価格:990円 |
![]()
アウトプットのメリット
インプットとアウトプットとは?
そもそも、インプットとアウトプットとは何でしょうか?
インプットとは、情報を外部から自分の中に「入力」すること、つまり「読む」「聞く」「見る」を指します。本を読んだり、人の話を聞いたりすることです。
アウトプットとは、入ってきた情報を脳の中で処理し、外の世界に「出力」すること、つまり「話す」「書く」「行動する」を指します。
さらに、インプットとアウトプットは、別の言い方に置き換えることができます。
インプット → 受動型(人に言われたとおりにやる)
アウトプット → 能動型(自分で考え、自分から動く)
上記の内容から、インプットよりアウトプットに重きを置く理由がなんとなく見えてきたのではないでしょうか。
大事なのは、インプットの量よりも、アウトプットの量なのです。
運動性記憶は忘れにくい
インプットとアウトプットの大きな違いは、アウトプットは「運動」であるということです。
たとえば教科書の内容を覚えるとき、インプット型の勉強法の代表的なものは「教科書を読む」ことです。読んで覚えることは、関連性がないもの同士を記憶するので「意味記憶」に相当します。この意味記憶は「覚えにくい」「忘れやすい」という特徴があります。覚えるのに時間がかかる割に忘れやすいため、効率が悪くなります。
一方、アウトプット型の勉強法は「教科書を音読する」「ノートに書く」「問題を解く」「友達と教えあう」などになりますが、これらの場合、手や口の運動神経を使います。
運動神経を使った記憶は「運動性記憶」となりますが、この運動性記憶には「極めて忘れにくい」という特徴があります。「自転車に乗る」も運動性記憶にあたります。
「書いて覚える」「声に出して覚える」ようにすると運動性記憶として記憶することができ、忘れづらくなる
インプットとアウトプットの理想は3:7
現在は、インプット中心の勉強ばかり行われています。
しかし前述したように、インプットの量よりも、アウトプットの量を増やすことが重要です。
インプットに費やす時間は3割にして、7割の時間をアウトプットに使うのが、最も効果的な勉強法といえます。
たとえば、教科書を20分読んだら、40分は問題集を解いたり、ノートをまとめたり、手を動かして書くための時間に使うということです。
また、「声に出す」「音読する」などの「話す」のもアウトプットですが、指を器用に動かす「書く」作業の方が、脳に複雑な作業を要求します。
つまり、「話す」よりも「書く」ほうが、圧倒的に脳を活性化させ、記憶に残りやすくなります。
8割の人が「話すのが苦手」
次に、アウトプットの1つである「話す」に関してです。
実は、大人でも8割以上の人がコミュニケーションに苦手意識を持っているそうです。
人と話すのが苦手という人は、得意な人に比べて、子供のころのコミュニケーションの量が単純に少ない場合が多いのだそうです。つまり、「こなした数」の問題なのです。
では、コミュニケーション能力を伸ばすには、どうしたらいいのでしょうか。
それは、徹底的に話す練習をすることです。
具体的には次のことに取り組みます。
自己肯定感を高める
コミュニケーションが苦手な人ほど、「悪い方の結末ばかりを予想しがち」という特徴があります。「相手に嫌われたらどうしよう」と気になってしまうのです。それは「自己肯定感の低さ」が原因かもしれません。
自己肯定感を高めるために効果的なのは、小さな成功をたくさん積み上げることです。
「今日は自分から話しかけた」「気持ちの切り替えがうまくできた」等、それほど大きなものでなくても、少しずつ積み上げていくことで自己肯定感が育っていきます。
そのためには、自分からたくさん行動して、たくさん経験するしかありません。
「ポジティブ」を口に出す
普段の会話で重要なことは、「ネガティブなことは避けて、ポジティブなことを話す」ということです。
毎日、「楽しい」個を毎日アウトプットする人は「毎日楽しい」という印象と記憶が残ります。「つらい」3個を毎日アウトプットする人は「毎日つらい」という印象と記憶が残ります。
つまり、「毎日が楽しい人生」なのかどうかは、実際に何が起きるか以上にポジティブとネガティブのどちらをアウトプットするかによって決まるのです。
また、ポジティブなアウトプットはポジティブな人間関係を築き、ネガティブなアウトプットはネガティブな人間関係を築くのだそうです。
「書く」ことの効果
では、次にアウトプットの1つ「書く」ことについてですが、次のような効果があります。
記憶力が良くなる
先述したように、インプットに時間をかけるより、アウトプットに時間を費やすほうが忘れにくいと書きました。
それは、いくら素晴らしいインプットをしても、そのままにしていたら、そのときの感動や感情、情報は時間とともに失われ、どんどん曖昧になっていくからです。
「書き出す」という作業によって、そのときの「脳内」の状況を写真に残すように鮮やかに記録に残すことができるのです。
「書く」ことは「記憶する」ことそのもの
書けば書くほど記憶に定着する
考える力が身につく
「書く」という作業は、頭の中のまとまりのないものをいったん取り出してきれいに整理していくということです。
映画を観たり、本を読んだら感想を書くというアウトプットのトレーニングを続けていると、頭の中を整理して考えをまとめる、思考力のトレーニングになります。
ごちゃごちゃした経緯や状況を文章にする、つまり「言語化」することで、思考力、分析力など、順序立てて考える力が養われます。
失敗ではなく「エラー」
次に、アウトプットの1つである「行動」についてです。
「行動する」とは、インプットによる気づきを得て、実際にそれを始める、さらに続けていくことです。
行動すると、うまくいかないことも出てきます。
失敗したり、うまくいかなかった経験をして、さらに原因がわからなくて同じ失敗を何度も繰り返すと、「なんて自分はダメな人間なんだ」と自己肯定感が下がります。
もう失敗したくないからとチャレンジもしなくなります。そうなると自己成長も止まってしまいます。
そんなとき意識したいのが、失敗や不本意な出来事をすべて「エラー」だと捉えることです。
行けない道を1つずつ消していって、最後に正しい道がみつかります。それをやらない限りは正しい道には行きつかないのです。
つまり失敗しているように見えても、実はデータを集めているのです。
後悔しない決断術
最後に、「決断術」についてです。
人生を後悔せずに過ごすためには、「自分で決断する」ことが大事です。
「自分で決められない」「優柔不断で、決めるのにいろいろ迷ってしまう」という方も多いのではないでしょうか。
そこで、ものごとを決断する際のおすすめの「決断術」があります。それは次の3つです。
- 最初に思いついた方を選ぶ
- ワクワクする方を選ぶ
- 5秒で決める
最初に思いついた方を優先する方がいい理由は、その人の本心が最初に出てくるからです。
最初に出てくるのがその人の「直感」であり「心の声」と言えます。
それに対して、後から出てきたものは「理性」です。
もしかしたら「常識」や「打算」「言い訳」かもしれません。
②と③も同様です。
「ワクワクする」ということは、脳内にドーパミンが出ているということです。
ドーパミンが出ると、やる気や集中力、記憶力、学習機能などが高まり、脳のパフォーマンスもアップします。
迷ったらワクワクした方を5秒で選ぶ
 |
極アウトプット 〜「伝える力」で人生が決まる〜(小学館YouthBooks)【電子書籍】[ 樺沢紫苑 ] 価格:891円 |
![]()
感想
今回、本書を読んで感じたことは、「とにかく実践あるのみ!」ということです。
いくら言葉だけ吸収しても、行動しなければ意味がありません。
私自身、コミュニケーションに苦手意識があり、もう克服しなくてもいいかなとすら考えていました。
しかし、今回本書を通してアウトプットの可能性について学び直した結果、何度でもチャレンジしてみようと前向きな気持ちにさせてくれました。
一朝一夕にはいかないと思いますが、トライ&エラーを何度でも続けて頑張ってみようと思います。
それでは、今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。