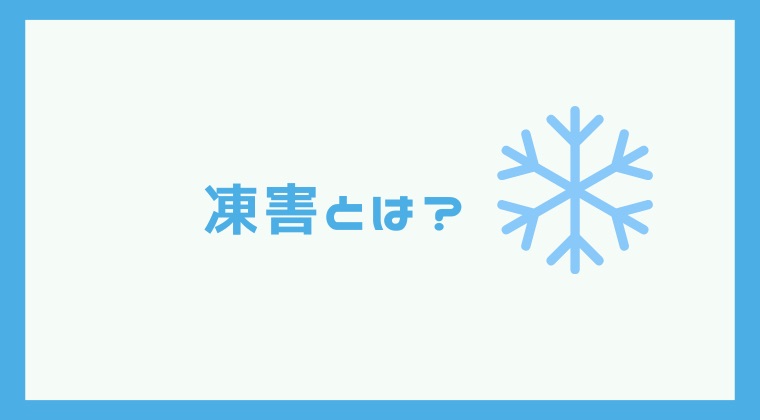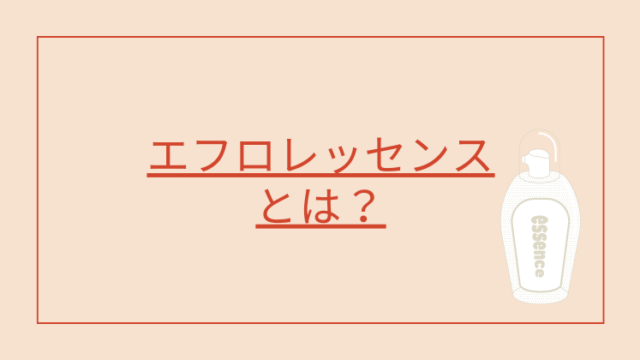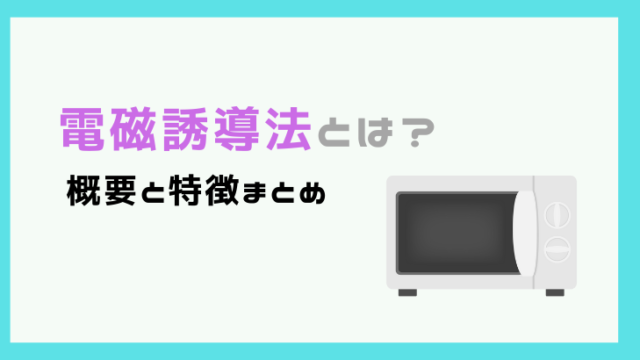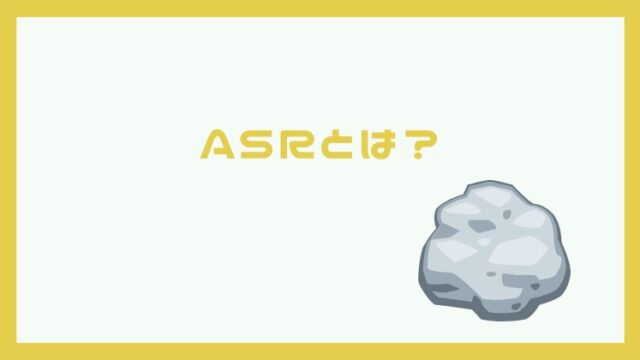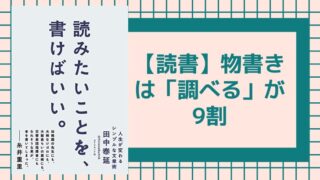劣化機構のひとつである凍害。
今回は、凍害についてまとめてみようと思います。
凍害とは
コンクリート中の水分が凍結と融解を繰り返すこと(凍結融解作用)により、コンクリートが表層に近い部分から徐々に破壊していく現象のことをいいます。
水は凍結するときに約9%の体積膨張を起こします。
コンクリートの含水量が多いほど、水の凍結による膨張圧も大きくなるため、多くの水分が供給される環境では凍害の進行は速くなります。
コンクリート中の自由水が凍結するときに、まず大きい空隙中の水が凍結し、次いで小さな空隙中の水が凍結します。
また、凍結融解の繰り返し回数が多い方が劣化進行は速くなります。そのため、同一コンクリート構造物において、常に雪の中にある部分よりは、雪の解けやすい部分の方が凍害を受けやすいとされています。
北面より南面のコンクリートに凍害が生じやすい
凍害による劣化形態
凍害による劣化形態として、下記のようなものが挙げられます。
ポップアウト
吸水量が多い骨材が凍害を受けることによって膨張し、コンクリート表面が剥離する現象
スケーリング
コンクリート表面が薄く剥離する現象
微細ひび割れ
網状の細かいひび割れが発生する
凍害を防ぐには
コンクリート中の水分の凍結は、コンクリート中の細孔分布にも大きく影響を受けます。凍害抵抗性の指標のひとつとして気泡間隔係数が用いられます。
凍結融解の繰り返し作用を受けるおそれがある場合には、気泡間隔係数を200~250㎛以下とするのがよいとされています。
また、水セメント比(W/C)を小さくして、緻密なコンクリートにするのも有効です。AE剤やAE減水剤を用いて適度な空気を連行することが必要です。
問題
では、最後に下記の○×問題を解いてみましょう。
「ベランダ、ひさし、パラペットなどの突出部は、外壁面に比べて凍害を受けやすい」
答えは下にスクロールしてください。

正解は〇です。
水に濡れる機会の少ない外壁に比べて、ベランダ、軒先、ひさし、パラペットなどの突出した箇所や屋外階段、屋上スラブ面などは凍害を受けやすいとされています。
今回は以上になります。
ありがとうございました。