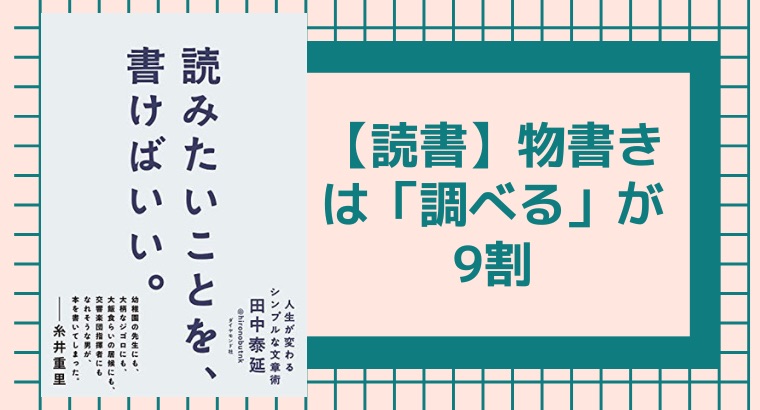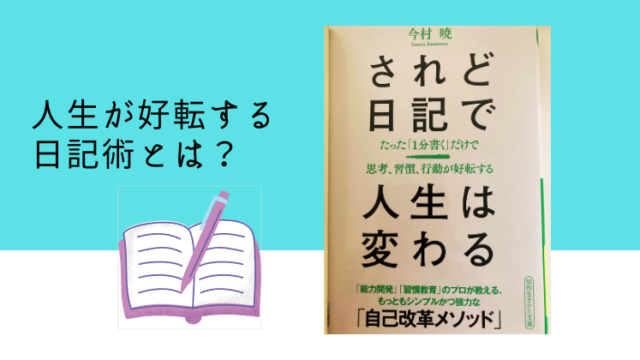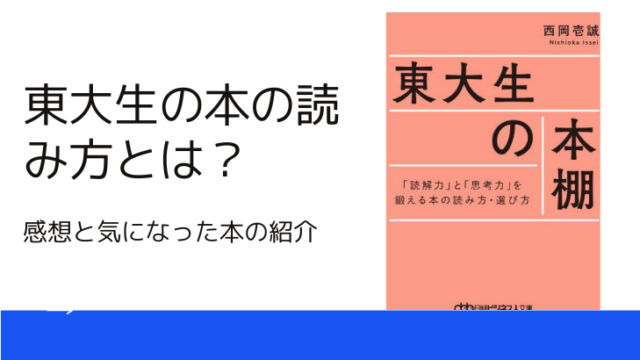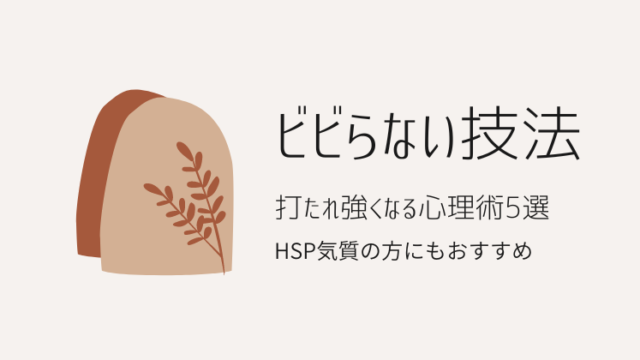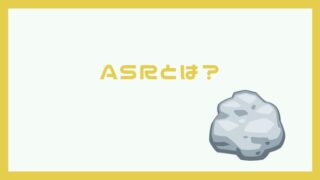潔いくらいシンプルな表紙とタイトル。
ひときわ存在感を放つこの本を、気になっていた方も多いのではないでしょうか。
今回は、こちらの本の魅力をご紹介したいと思います。
主に記す内容は以下の3点です。
ネットで読まれている文章の9割は「随筆」
ネットで読まれている文章の9割は随筆である、と著者は綴っています。
随筆とはなんだろう?とまず思いました。
著者は、随筆について以下のように定義しています。
「事象と心象が交わるところに生まれる文章」
事象とは、見聞きしたことや、知ったこと。
心象とは、事象に触れて心が動き、書きたくなること。
その2つがそろってはじめて「随筆」が書かれる。人間は、事象を見聞きして、それに対して思ったことや考えたことを書きたいし、また読みたいのである。
これを読み、私の頭には浮かぶものがありました。ツイッターです。
たとえば、「〇〇のパンケーキを食べた」という呟きがあったとします。
これだけだと、ふーん、と思うのみかもしれません。
それがもし、「〇〇のパンケーキを食べた。とても美味しかったからまた食べたい」
というふうに、ちょっと感想が添えてあると、へぇ、行ってみたいな、という気持ちになりやすいと感じました。
物書きは「調べる」が9割9分5厘6毛
著者は以下のように述べています。
書くという行為において最も重要なのはファクト(文脈)である。ライターの仕事はまず「調べる」ことから始める。そして9割を棄て、残った1割を書いた中の1割にやっと「筆者はこう思う」と書く。
つまり、ライターの考えなど全体の1%以下でよいし、その1%を伝えるためにあとの99%以上が要る。
上記はあらゆる書き手に通じる言葉かなと思います。
個人的には、調べたことをわかりやすく相手に伝えるために、論理的に話す(書く)能力を鍛える必要があると感じました。
ちなみに、資料の調べ方についても詳しく書いてあるので、おすすめです。
だれかがもう書いているなら、読み手でいよう
この一文を目にしたときは、強く衝撃を受けました。
たとえば、これからブログを始めようとしている人がいるとして、さて何か記事を書こうとしたとき、ほとんどのことはすでに誰かに書かれているのでは?と思ったからです。
著者は、さらに以下のように綴っています。
「『わたしが言いたいことを書いている人がいない。じゃあ、自分が書くしかない』読み手として読みたいものを書くというのは、ここが出発点なのだ。(中略)だが、『いまさら書かなくていいことは書く必要がない』という事実はある意味、ラクなことだ。特段の新しいものの見方も疑問もなく、読み手で構わないなら、読み手でいよう。」
ここを読んで、ああ、と腑に落ちました。
この「読み手で構わないなら、読み手でいよう」の部分が肝だと思いました。
たとえば、私にとっては同人誌がそうです。推しや好きなジャンルの本は何冊でも読みたいと思います。たとえテーマが被っていたとしても、内容が稚拙だとしても。
自分が調べたいこと、何度読んでも大好きだと感じるものを書けば良い。逆に、わざわざ自分で調べたりしないし、そう何度も繰り返し読みたいとは思わないものは読み手でいればいい。そう感じました。
最後に
この本は私にとって指南書であり、辞書であり、エッセイでもあります。それほど多くの側面を持ち、情報がぎっしり詰め込んであります。
また、気づきや発見が多くあります。おそらく読み手によって、この本から抽出する内容、抱く感想は少しずつ異なるように思います。ぜひ、手に取ってみてください。
今回は以上になります。
ありがとうございました!