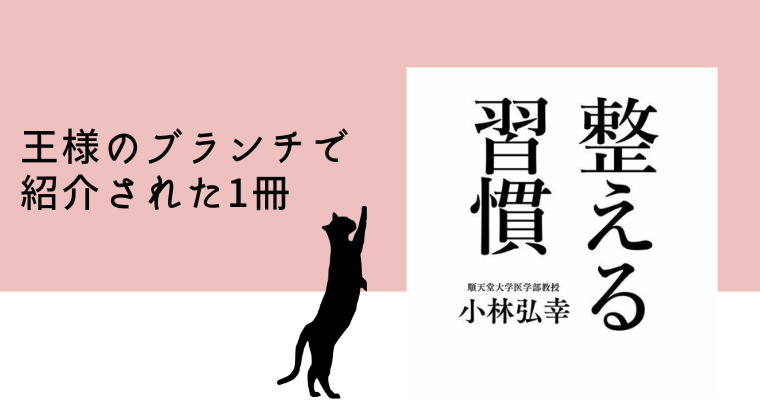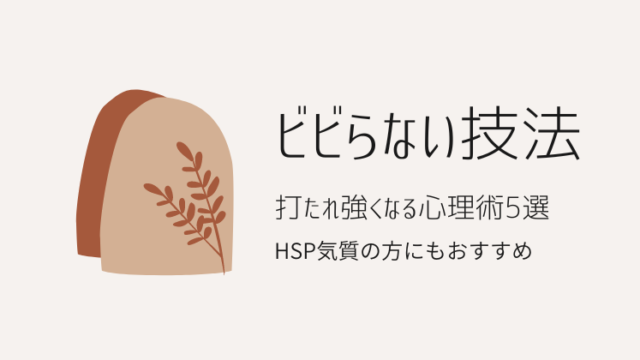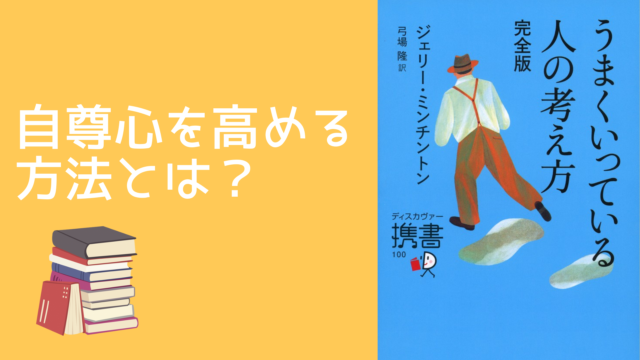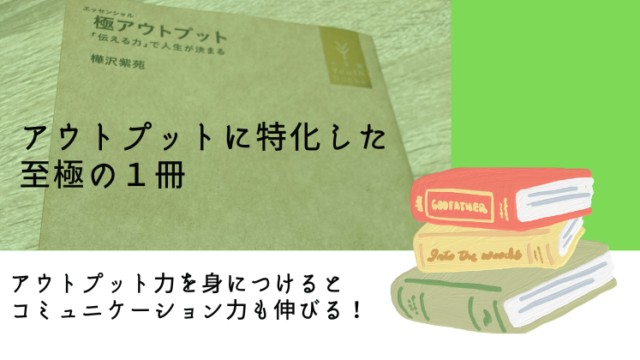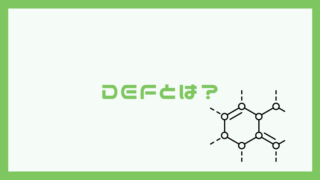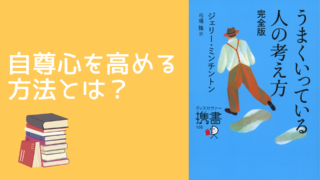今回は、小林弘幸著「整える習慣」を読んだ感想と、実際に私が生活の中に取り入れてみようと感じた部分を紹介させて下さい。
はじめに
本書はタイトルにある通り、習慣にまつわる内容が記されています。
「身の回りの整え方」
「時間の整え方」
「人間関係の整え方」
「体の整え方」
「食の整え方」
「行動パターンの整え方」
「メンタルの整え方」
「自分自身の整え方」
上記の8つの章で成り立っており、108の行動術が収録されています。
著者は順天堂大学医学部教授で、多くの一流スポーツ選手のコンディショニング・アドバイザーをされています。主な著書に「医者が考案した『長生き味噌汁』」「眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話」などがあります。
今回、私が紹介する行動術は次の5項目です。
・服を捨てると集中力が増す
・午前中の「勝負の時間」を無駄にしない
・昼食後の2時間は捨ててOK
・移動時間にも習慣をつくる
・大問題こそ小さく考え、ささいなことほど大きく考える
それでは、具体的に見ていきましょう。

服を捨てると集中力が増す
「服を捨てる?そんなこと?」と思うかもしれません。
しかし、「何かを選ぶ」という作業はストレス以外の何ものでもありません。
「選ばなきゃいけない」という状況は自律神経を乱し、コンディションを悪くする要因なのです。
クローゼットを開けたときくらいは、すっきりとストレスフリーな状態をつくっておくのがおすすめです。
ちなみに、身の回りの整え方としては他にも
・鞄に徹底的にこだわる
・窮屈な服や靴は選ばない
・シャツは「白一択」
・財布の整理を一日一回
などがあります。どれもすぐに実行できることばかりですね。
午前中の「勝負の時間」を無駄にしない
「集中力が高まる時間」「ものを考えるのに適した時間」、それは午前中であると著者は述べています。
いわば「勝負の時間」とも言える午前中に、重要度の低い仕事(メールチェックなど)をしたり、「何をしようか」と考えるのはもったいないそうです。
よって、最も良いのは「前日にto do リストを作っておき、午前中は100%その作業に集中できるようにしておく」というのが理想的と言えそうです。
昼食後の2時間は捨ててOK
昼食後、どうしても眠くなってしまって作業がはかどらないという人もいるのではないでしょうか。私はそうです。
午前中の勝負の時間とは真逆で、著者は、昼食後の2時間はほとんど仕事がはかどらないノンファンクション(非機能)な時間帯だと述べています。
よってこの時間にメールチェックや、ルーティンワーク、ミーティングや打ち合わせをセッティングするのが良いそうです。
移動時間にも習慣をつくる
時間を上手に活用したいと思うなら「移動時間に何をするか」を決めて行動することが重要です。こう聞くと、なんだか「1分1秒を無駄にするな」という風にも聞こえてしまいますが、決してそうではなく、「なんとなく時間を使っている」という状況が良くないのだそうです。
大事なのは「計画的にやっているか」。「移動時間はスマホゲームをする」「移動時間は寝る」など、ただなんとなくやるのと意識してやるのでは大きく違いがあるのです。
遊ぶときは遊ぶと決める、休む時は休むと決める、という意識が重要です。
大問題ほど小さく考え、ささいなことほど大きく考える
仕事や日常生活において、何かイレギュラーなことが起こるとすぐに動揺し、狼狽えてしまう私にとって、このマインドはけっこう大事かなと感じました。大問題が起こった時は深呼吸をして、水を1杯飲み、無理にでもいいから笑顔をつくり「さぁ困りましたね」とのんきな声で言う。反対に、日常的に起こるささいなミスほど軽く考えて放置するのは危険です。日々の小さなミスを放置し、ないがしろにする人は、結局は自分のコンディションを崩し、能力をフルに発揮できなくなってしまうからです。「日常的に自分の能力が発揮できていない」という状況こそ、見逃すことができない大問題です。
感想
本書は全体を通して読みやすく、とにかくわかりやすく、簡単で、行動に移しやすいというのがキーワードになっていると思います。
逆に言ってしまうと、目新しい情報はほとんどなかったように感じました。つまり良い習慣とは、難しいことをする必要はなく、ちょっとした意識の向け方や行動の積み重ねがより良い人生を作るカギなのかなと感じました。ここまで書いておきながら、なんだか耳が痛いです。
今回は以上になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。