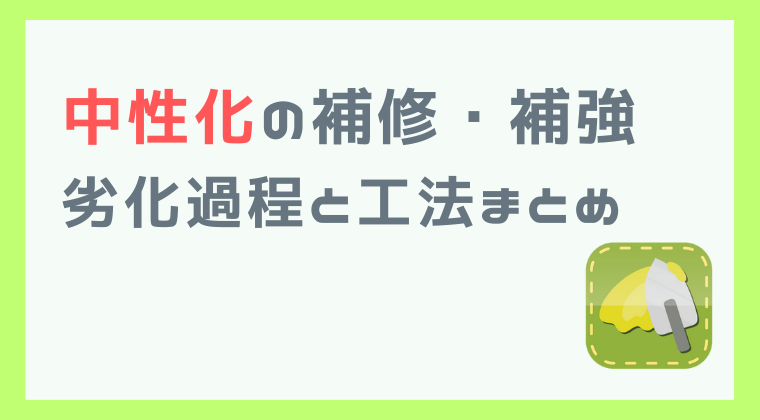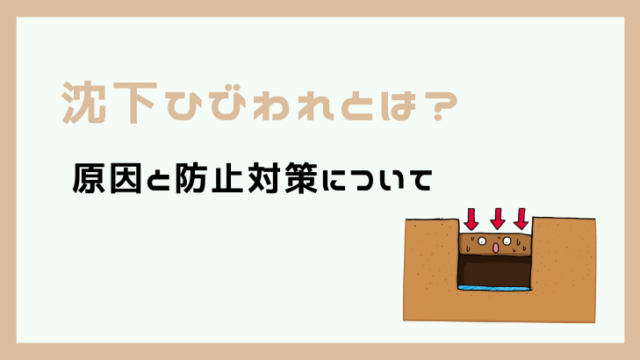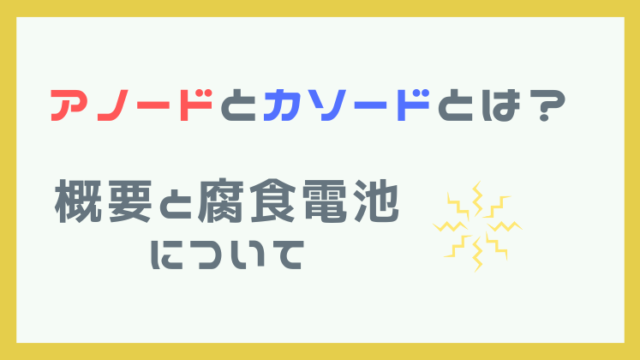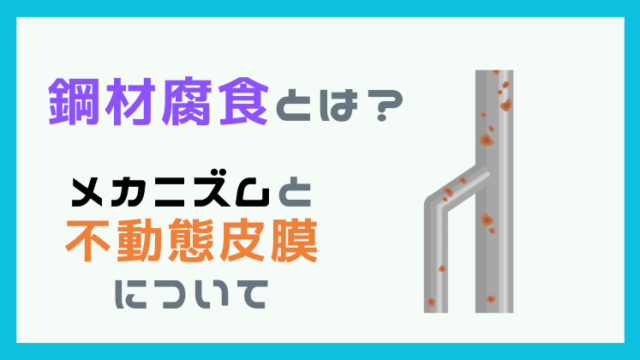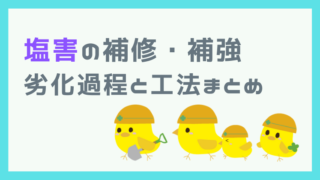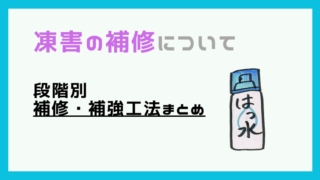こんにちは!
今回は中性化の補修・補強工法についてまとめてみます。
最後に問題もあるので、良ければ解いてみてください。
それではいってみましょう!
中性化の劣化過程と変状
まず、中性化により劣化した構造物の状態と、外観上のグレードについては次の通りです。
状態Ⅰ(潜伏期):外観上の変状が見られない。中性化残りが発錆限界以上。
状態Ⅱ(進展期):外観上の変状が見られない。中性化残りが発錆限界未満、腐食が開始。
状態Ⅲ-1(加速期前期):腐食ひびわれが発生。
状態Ⅲ-2(加速期後期):腐食ひびわれの進展とともに剝離・剝落が見られる。鋼材の断面欠損は生じていない。
状態Ⅳ(劣化期):腐食ひびわれの進展とともに剝離・剝落が見られる。鋼材の断面欠損が生じている。
加速期前期から、美観の低下(ひびわれ、さび汁、鋼材の露出)が生じます。
加速期後期から、美観の低下に加えて、第三者への影響(剝離・剝落)が生じます。
劣化期から、安全性において耐荷力・じん性の低下(鋼材断面積の減少や、浮き・剝離によるコンクリート断面の減少)が生じます。
中性化の補修・補強工法
次に、中性化の各劣化段階において適用できる補修・補強工法については次の通りです。
潜伏期:ひびわれは発生しておらず、劣化要因の遮断、劣化速度の抑制に対する予防的対策をとる。表面被覆工法や含浸材塗布工法が有効。
進展期:鉄筋腐食から腐食ひびわれ発生に至る段階で、劣化因子の遮断、劣化速度の抑制に対する対策をとる。潜伏期の工法に加えて、再アルカリ化工法、断面修復工法が有効。また、ひびわれが生じた部分では、脆弱部を除去する。
加速期:腐食ひびわれが発生し、急速に腐食が進行する段階。ひびわれ、浮き部のコンクリート除去、かぶりコンクリートはく落防止を行う。進展期と同様に、再アルカリ化工法、断面修復工法が有効。
劣化期:耐荷力低下段階で、補強の対象となる段階。劣化因子の除去、耐荷力、変形性能の改善等の対策をとる。再アルカリ化工法や断面修復工法に加えて、補強として接着工法、巻立て工法、増厚工法、外ケーブル工法などが有効。さらに劣化がひどい場合は打換えを行う。
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
コンクリート構造物の表面被覆工法に使用する、樹脂系塗布材料に求められる性能に関する次の記述が、適当か不適当か選択してください。
「中性化を抑制するためには、防水性に優れ、かつガス透過性の大きい材料を塗布するのが良い。」
答えは下にスクロールしてください。
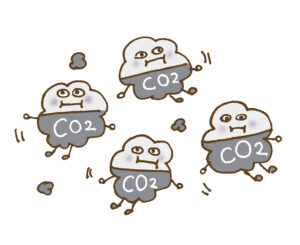
正解は、不適当です。
ガス透過性の大きい、という部分が誤りです。
中性化を抑制するためには、劣化因子である二酸化炭素の浸入を防止する必要があるため、ガス透過阻止性が重要です。
それでは、今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。