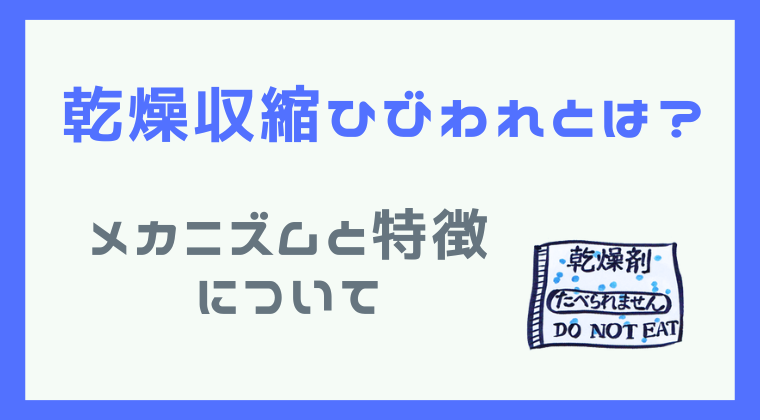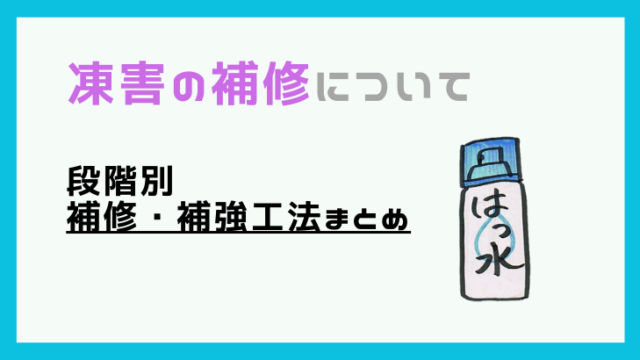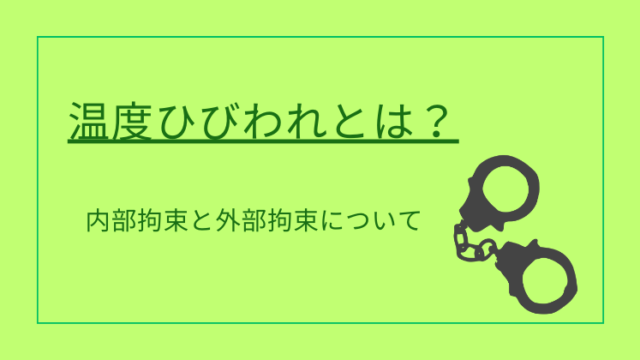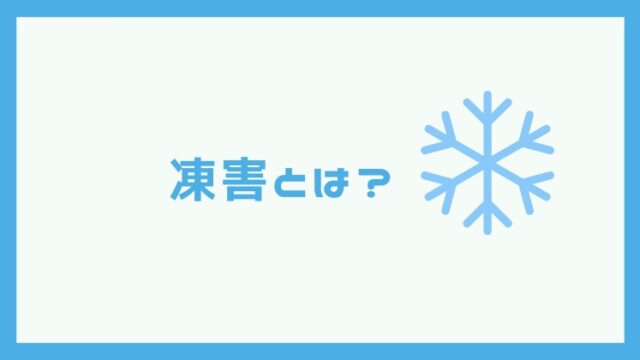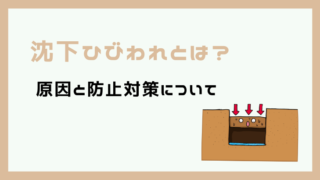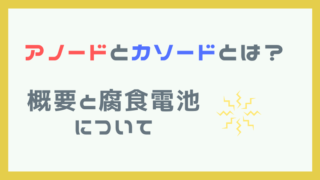今回は乾燥収縮ひびわれについてまとめてみようと思います。
最後までお付き合いいただけると幸いです。
乾燥収縮ひびわれとは?
コンクリートは、乾燥収縮、温度変化、自己収縮、水和収縮などで収縮する性質を持ちます。このような収縮が既設構造物や既設部材、部材の内部の鉄筋などにより拘束されて生じるひびわれを収縮ひびわれと呼びます。
このうち、乾燥によって生じるひびわれを乾燥収縮ひびわれと呼びます。
メカニズム
コンクリートが収縮すると、部材は短くなります。自由に収縮すれば応力は生じませんが、実構造物では部位や材料の違いから収縮の大きさが異なり、収縮の大きい箇所は小さい箇所の拘束を受けます。このとき、大きな収縮を生じた部材が収縮の小さい部材や収縮する部材の内部の鋼材により拘束を受けるとひびわれが生じます。
コンクリート中の水が乾燥に伴って逸散する際、小さな毛細管間隙に作用する負圧が増大する
特徴
乾燥収縮ひびわれの特徴として、次のことが挙げられます。
- 部材の乾燥は内部よりも表面のほうが卓越するため、部材表面にひびわれが発生する
- 乾燥収縮によるひびわれは、部材の乾燥の程度と拘束の程度などにより異なりますが、壁・床スラブなどの長辺方向に直角に、等間隔に、あるいは柱・梁などに拘束された壁・床の際、コーナー部・入り隅に斜めに発生するものが多い
- 壁・床スラブなどに開口部がある場合は、開口部の隅角部に斜め方向あるいは開口部の縁に直角方向にひびわれが発生する
- 横に長い建物では、低階層の躯体が、乾燥しにくい地中梁などに拘束されて壁の両端部に斜めに、逆八の字形に発生する
乾燥収縮ひびわれが発生しやすいのは、体積に対して表面積が大きい構造物や、単位水量が多い場合などが挙げられます。
防止対策
収縮ひびわれの防止対策には、収縮を小さくする方法と拘束を小さくする方法があります。コンクリートが収縮する要因としては、セメントの水和反応に伴う自己収縮があり、単位セメント量を低減すると収縮も小さくなります。また、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメントの使用も収縮を低減するのに有効です。
乾燥収縮量を低減するには、単位水量の小さい配合とすることと、乾燥収縮の小さい骨材の使用が効果的
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
次の記述は適当か、不適当か選んでください。
「コンクリートの中に配筋される鉄筋は、コンクリートの乾燥収縮に起因するひびわれの発生を防止する効果がある」
適当か、不適当か。
答えは下にスクロールしてください。

正解は不適当です。
コンクリートが乾燥収縮すると、内部に配されている鉄筋はコンクリートの収縮を拘束するので、ひびわれが発生しやすくなります。しかし、ひびわれが分散されて、1本1本のひびわれ幅は小さくなるために、ひびわれが構造体に及ぼす悪影響を小さくすることができます。コンクリートの乾燥収縮は、コンクリート材料の特性であり、鉄筋が配筋されていても乾燥収縮によるひびわれの発生を防止することはできません。
それでは、今回は以上になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。