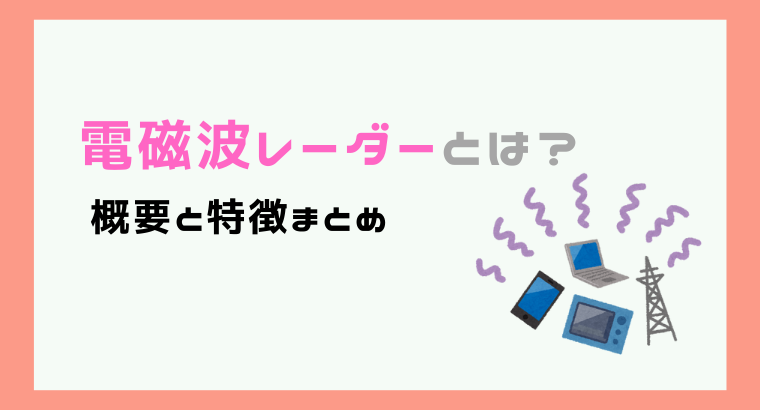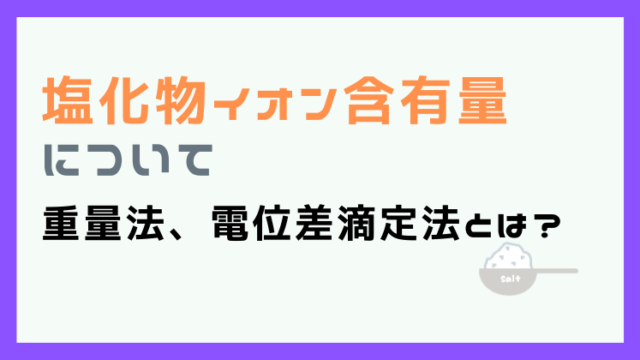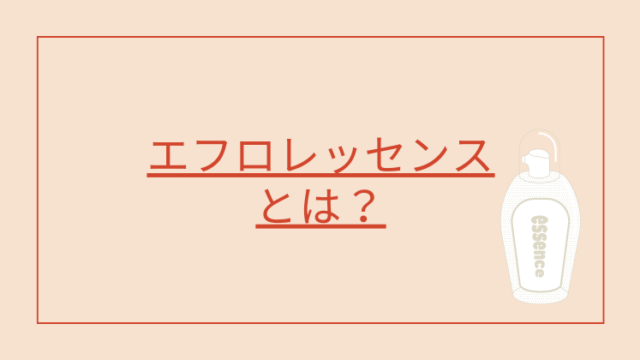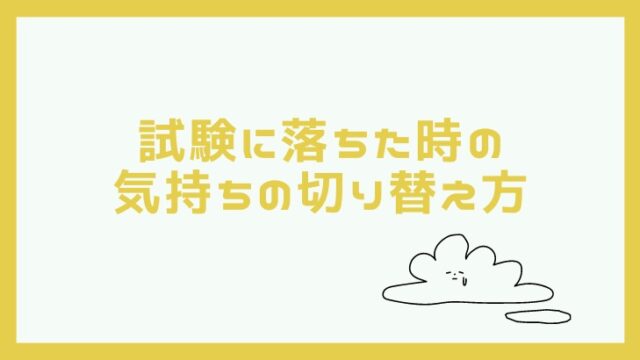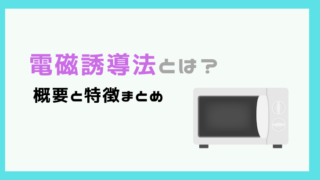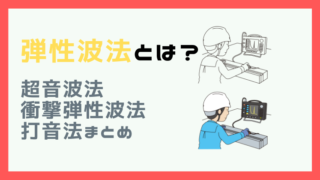こんにちは!
今回は電磁波レーダーについてまとめてみます。
最後に問題もあるので、良ければ解いてみてください。
それではいってみましょう!
電磁波レーダーとは?
概要
電磁波レーダーとは、コンクリート構造物内の鉄筋、埋設物およびコンクリート性状(躯体厚、空洞等)の調査方法の一つです。航空用、船舶用、気象用など、様々な分野で利用されている非破壊試験法です。
電気的性質(比誘電率、導電率)の異なる物体との境界面で電磁波が反射するという性質を利用して、電磁波が反射物体まで往復する時間を測定し、欠陥や鉄筋の深さ、部材厚を求めます。
取り扱いが簡単かつ短時間で広範囲の調査が可能で、すぐに結果が得られます。
比誘電率とは、物質の電気的特性を示すパラメータのこと
目的
測定目的は主に次の3つです。
- 内部欠陥の検出(空洞、豆板など)
- 部材厚の測定
- 鉄筋の検出(鉄筋間隔、かぶり)
適用箇所
適用箇所は、鉄筋・配管、ひびわれ、はく落、空洞、躯体厚(トンネル覆工)などです。
周波数
周波数が大きいと減衰が大きく、小さいものが対象です。遠くや大きいものは周波数を小さくします。
鉄筋などの埋設物探査の場合には800MHz~2GHz、空洞調査や部材厚の測定では400MHz~1GHzが推奨されています。
配筋について
基本的には埋設物や空洞部の調査で、鉄筋径などは測定できません。
特徴と留意点
電磁波レーダーの特徴は、次の通りです。
埋設物調査としては、鉄筋、埋設管などの埋設物の平面的位置や深さ方向の位置(かぶり)を検出することができる
コンクリート性状調査としては、躯体厚や空洞を検出することができる
コンクリート内へ放射された電磁波が、コンクリートと電気的性質の異なる物体(鉄筋、埋設管、空洞など)との境界面で反射する時の往復の伝播時間から、反射物体までの距離を算出する
乾燥状態にあるコンクリートの方が電磁波の伝播速度は速い
鉄筋径など、埋設物の太さの測定は難しい
周波数が低いほど減衰が小さく、より遠くのものを探査できるが、小さなものは探査できない
周波数が高いほど減衰が大きく、近くのものしか探査できないが、より小さなものを探査できる
留意点としては、次のことが挙げられます。
水平方向の精度は高いが、深さ方向の精度は、コンクリートの比誘電率の推定精度に影響される
コンクリート表面が水で濡れている状態では、比誘電率の影響を受け、測定精度が低下する
埋設管などの非電磁性体も検出できるが、基本的には反射物体が鉄筋か埋設管かを区別することはできない。しかし、埋設管が塩ビ管であるとき、鉄筋と比誘電率が異なるため、これらが同時に埋設されている場合、両者の区別が可能
コンクリートの比誘電率は、主に含水率の影響を受けるため、絶えず変化する(コンクリートにおける一般的な値は乾燥時で4~12程度、湿潤時で8~20程度)
問題
それでは、最後に次の問題を解いてみましょう。
電磁波レーダ法による鉄筋のかぶりの推定に関する次の記述が、適当か不適当か選択してください。
「コンクリート中に入射する電磁波の周波数が高いほど、かぶり(厚さ)の推定のための距離分解能は向上し、探査できる深さは浅くなる。また、湿潤状態にあるコンクリートは、乾燥状態のコンクリートに比べて電磁波の伝播速度は小さくなる。」
答えは下にスクロールしてください。
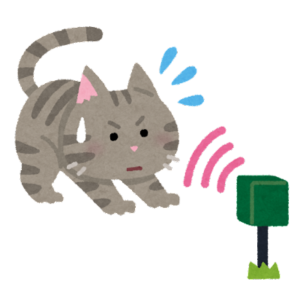
正解は、適当です。
電磁波レーダ法では、周波数が高いほどかぶり(厚さ)推定のための距離分解能は向上するため、より小さなものを探査できますが、その反面、減衰が大きいため探査できる深さは浅くなります。また、空気よりも水の方が比誘電率は大きいため伝播速度は速いことから、湿潤状態にあるコンクリートは乾燥状態にあるコンクリートに比べて電磁波の伝播速度は小さくなります。
それでは、今回は以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。