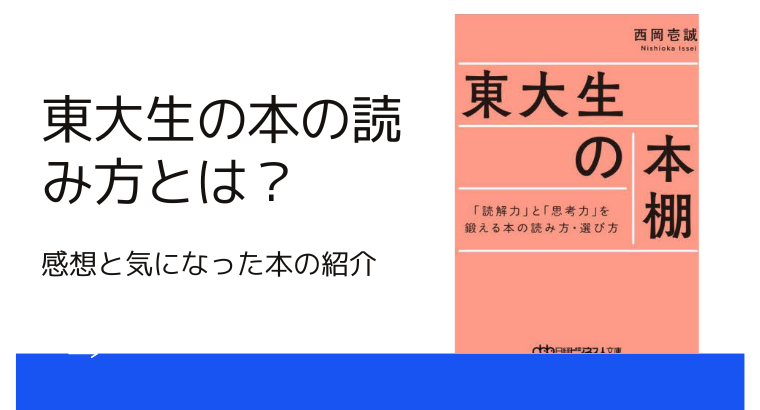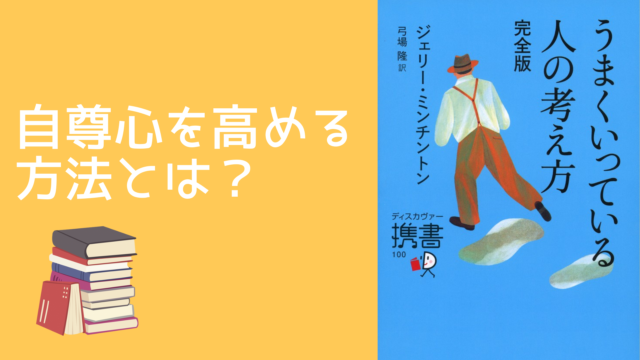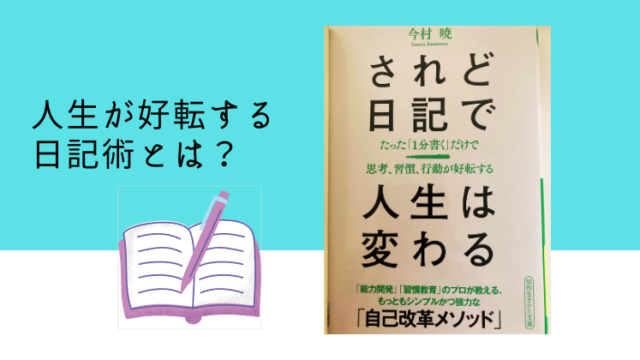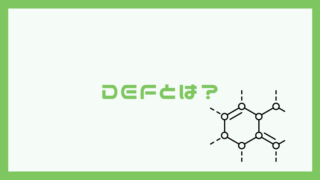こんにちは。冬です。
今回は、西岡壱誠さん著「東大生の本棚」を紹介させてください。
この記事は下記のような人におすすめです。
・東大生が読んでいる本が知りたい
・東大生がどのように読書をしているのか知りたい
・今後読む本の参考にしたい
本の構成
この本は2部構成になっており、1章では東大生の本の読み方、2章では東大生が実際に読んでいる本の紹介がされています。
東大生の本棚
東大式「読んで終わり」にしない本の読み方
「東大生はどうして読んだ内容を忘れずに活用できるのか?」「せっかく読んだ本も、すぐに内容を忘れてしまう」
このような声に対して、著者は次のように述べています。
東大生の読書にはある法則があります。それは、感想です。東大生は、本を読んだ後、「感想」をアウトプットするから忘れないのです。
アウトプットによって得られる効果は2つあります。
・感情が明確になる
どんな本でも、内容が理解できていればなんらかの感情が発生しているはずです。重要なのは、その感情を自分の中で言語化するという行為です。言葉にしてはじめて、自分がその本に対してどう考えているのか分かります。そうすると、自然と記憶として定着することにつながります。
・受け身から脱却できる
本を読んでいると、どうしても受動的になってしまいがちです。書いてある内容をそのまま呑み込み、疑うこともなく淡々と読み進めてしまう。しかし、それはあまり効果的な読み方とは言えません。受け身の読み方では、記憶に残らないからです。そんな受け身から脱却する歩となるのが「感想」なのです。本に対して思ったこと、考えたことを言葉にして、他人に言える状態にするというのは、内容を自分で噛み砕く「能動的な」行為です。「後から感想を言おう」と考えるだけで、「もっとちゃんと読まなければ!」と受動的な読書から脱却することにつながります。
・アウトプット→「感情」が明確になる→記憶に残りやすい
・「感想」は受け身から抜け出す第一歩
東大生は、同じ本を何度も読み返す?
東大生へのアンケート結果が印象的だったので以下に述べます。
内容は、幼少期の読書経験について問うもので、1冊の本を何度も読んでいた?それとも多くの本を読んでいた?というもの。
結果は、「1冊の本を何度も読んでいた」が63%、「多くの本を読んでいた」が37%でした。
それに対して著者は、同じ本を何度も読むことによって読解力を鍛えているという見解を述べています。
同じ本を何度読むことによって彼ら彼女らが身につけているのは、文章のリズムです。一度読んだだけでは身につかない、物語の語り口や展開の仕方を、何度も読むことによって自分のものにしているのです。(中略)何度も読むのがいいのは、子供の時に限った話ではありません。東大生の中には、教科書をボロボロになるまで読み込んで勉強したという学生が非常に多いです。多くの参考書を読むのではなく、ひとつの参考書を丁寧に読み込むことでこそ、東大入試に必要な力(読解力)が得られるわけです。
これは、様々な場面で活かせる考え方だなと感じました。
たとえば資格試験の勉強において、何冊も参考書や問題集を買いこむのではなく、自分にあった書籍を選び、理解できるまで何周もやりこむ。
または、ライターやブロガー、小説家やエッセイストなどの物書きを目指すのであれば、「こんなふうに書きたい!」と思う自分の理想の作家さんの文章を何度も読みこむ、または写経し、文章のリズム、接続詞の効果的な使い方、話の展開などを自分の文章力に落とし込むことができるのではないかなと思いました。
・教科書はボロボロになるまで読み返す。
・どんな本でも繰り返し読むことで「読解力」がアップする。
東大生の本との付き合い方
本は図書館で借りるか、書店で購入するか。意見が分かれるところではないかと思います。
これに対し著者は、本は購入したほうが断然いいと言います。その理由として以下のことを述べています。
本は読み手によって無限に姿を変えるものだから、本は買った方がいいと思います。もちろん、文章自体が変化するということはありません。しかし、文章が変わらなくても、読み手の状態が違えば確実に本の中身は変わります。自分がどういう状態にいて、どういう時にその本を手に取るかによって、本から得られるものはまるで違うものになります。だからこそ、本がいつでも好きなタイミングで手に取れる状態をつくるのが理想的なのです。(中略)新しい本を読み進めるうちに、以前読んだ本を読み返したくなることがあります。不思議なもので、本というのは、読めば読むほど、「あ、この本で述べられている概念、あの本でも読んだな」「この内容、あの本でも述べられていたはず」と読み返したくなるものです。
教養とは、情報と情報、知識と知識を結びつける力です。新しい本を読み、新しい情報を仕入れると同時に古い情報を更新することで教養が高まるのです。教養を高める上で「読み返し」は必須。でも、図書館で借りた本では、必要な時に「読み返し」ができません。「新しい情報」と「古い情報」をつなぐために、何度も本を読み返す。そのためにも、いつでも手の届く場に本がある環境をつくることが大事なのです。
「読み返し」が教養を高める、というフレーズは、私にとって金言のように感じました。本を買うお金は惜しまなくていいのだ、と背中を押してもらったような気持ちになったからです。それと同時に、思い出すことがありました。
別の記事で紹介している、田中泰延著「読みたいことを、書けばいい。」の中で述べられていたことなのですが、「調べ物をする時には図書館を利用する」ということを言っていたな、と思い出したのです。図書館と書店、読書の目的によって使い分けてあげればいいんだろうな、と思いました。たとえば大学生のレポートや、ライターが執筆する記事の内容に関する調べ物には図書館を利用する、自己投資としての読書なら書店で本を買う、など。両方うまく活用できればいいなと感じました。
・読書で「新しい情報」と「古い情報」をつなぐ
・教養を高めるうえで「読み返し」は必須
気になった本3冊
ここからは、2章以降の中で紹介されている本の中から、私が特に気になった本4冊をご紹介させてください。
乙川優三郎著「ロゴスの市」
この本に対して、著者は次のように紹介しています。
文章が美しいかどうか、という観点で本を読んだことはありますか?僕はなかったです。でも東大生の中には、そうした「文章の美しさ」を気にして読む人がいるのです。そんな東大生の中から挙がった本が、この「ロゴスの市」です。
こんな魅力的な紹介文を読んでしまったら、ぜひ手にとって確かめたいという衝動に駆られてしまうのは当然だと思います。
ロゴスの市
原研哉著「白 」
」
この本は、東大の現代文の入試でも出題されたことがあるそうです。さらに、「この本は絶対読んでおいたほうがいい」と話す大学生が何人もいるとのこと。この本に対して、著者は次のように述べています。
僕は、この本を読むことで、自分たちがどういう価値観の元に生きているのかを考えるようになりました。価値観や文化というのは、なかなか自覚する「きっかけ」がありません。知らず知らずのうちに、そういう考え方をしていた、ということだってあり得ます。しかし、日本人である「自分」を根本の根本まで辿っていくと、実は「白」という価値観に行き着くのかもしれない。
「白」という価値観ってなんだろう、とまず思いました。内容はもしかしたら難解かもしれません。でも、わたしはこの「白」というタイトルにシンプルに惹かれました。読みたいと思ったのは、実はそれが一番大きいです。
平原卓著「読まずに死ねない哲学名著50冊 」
」
ポップでかわいらしい表紙のこの本。著者は次のように紹介しています。
さまざまな哲学の名著の、解説と要約が載っています。コンパクトにまとまっているうえ、歴史的な背景・文脈などもセットになっているので、ただその考え方を知るのではなく、「どうしてそういう思想が生まれたのか」まで知ることができます。
哲学の名著、と聞くとわたしは難解なものを連想してしまいます。本も分厚かったりするし・・。でも内容は知りたい。そんな風に考える人はきっと少なくないのではないでしょうか。そんな人にこの本はぴったりだと感じました。
最後に
この本で紹介されている本は、累計177冊になります。そのうち、140冊は著者のおすすめなのですが、それは後ろのほうのページにおまけのように写真とタイトルだけ載っています。わたしは、それを眺めるだけでも楽しく感じました。誰かのおすすめ本を見るのが好きな人にも、この本はうってつけかと思います。
ちなみに著者のおすすめの中で紹介されていて、個人的に気になった2冊「小林弘幸著 整える習慣」と「佐渡島康平著 観察力の鍛え方」を購入してみました。こちらも読んだらレビューしようと思います。
今回は以上になります。ありがとうございました!