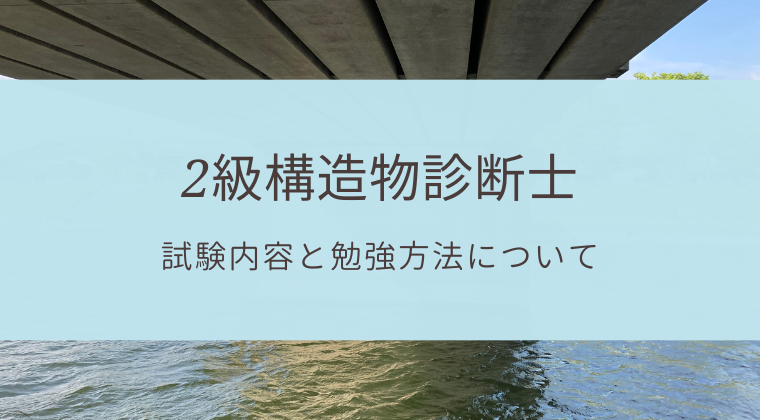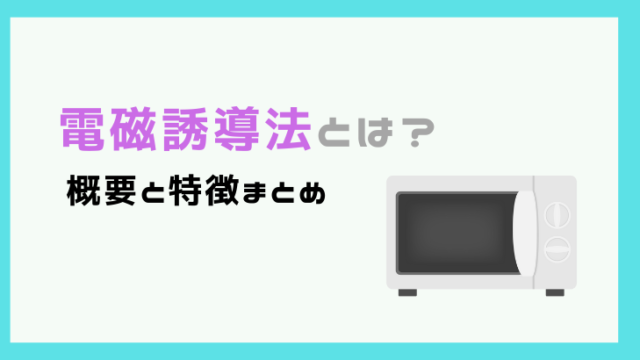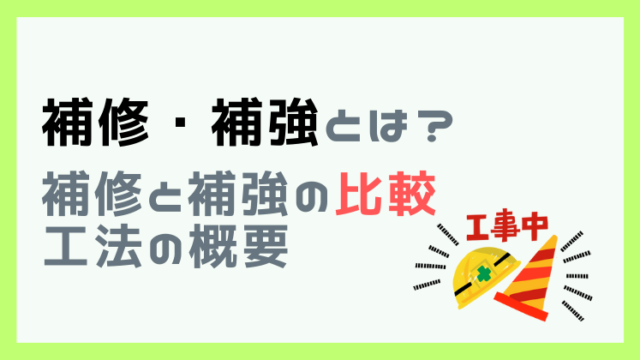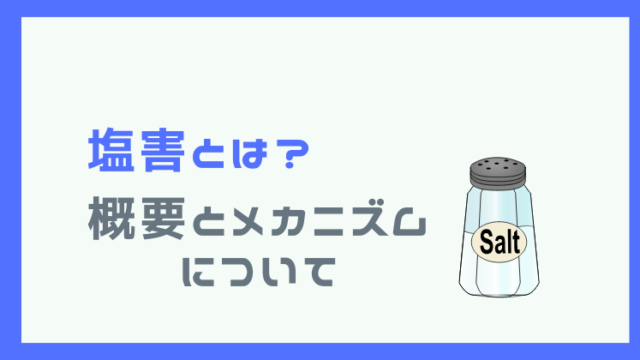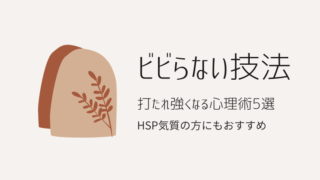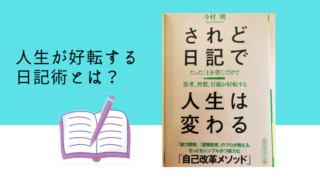今回は、2級構造物診断士試験を受験した際の試験内容や、勉強方法についてまとめてみようと思います。
勉強方法と参考図書、勉強した期間
勉強方法
まず勉強方法についてですが、具体的には以下のことを繰り返しました。
- 受験申し込みをした後送付されてくる分厚いテキストを、とりあえずぱらぱらっと読む
- 重要だと思う箇所に付箋を貼りまくる
- テキストを見てインプット、テキストを閉じてアウトプット(ノートに書く)
以上です。ひたすら繰り返します。
ただし、私の場合は同年にコンクリート診断士試験を受験する予定があったため、同時期にコンクリート診断士の問題集をやりこんでいました。そのため、コンクリートの劣化に関する問題への対策としては、コンクリート診断士の問題集が有効と言えそうです。
ちなみに、試験前に開催されたテキスト講習会には参加していません。(地方在住のため・・)
都合がつくのであれば、試験対策として受講した方がいいのかなと思います。
参考図書
参考図書は2種類使用しました。
1つめは、前述したようにコンクリート診断士の問題集です。
こちらを使用して、主にコンクリートの劣化について理解を深めました。
2つめは、土木鋼構造診断士の問題集です。
こちらは、身近に土木鋼構造診断士を受験した方がいたため、テキストをお借りして鋼の分野について理解を深めました。実際に問題を解くというより、眺めて雰囲気を掴む程度です。なくても問題ありません。
ちなみに、構造物診断士って、過去問の問題集とかないの?と思っている方も多いと思います。私も必死に検索した一人です。残念ながら、今のところないようです。
実際に受験した日も、試験問題を持ち帰ることができませんでした。
勉強期間
勉強した期間は、約半年だったと思います。(本腰を入れて、必死に勉強したのは3ヶ月ほどだったかも・・)
平日は1日1時間、土日は細切れに2時間ほど勉強していました。
ただし前述したように、コンクリート診断士の勉強も並行していたため、こちらの時間も合わせるともう少し多いかもしれません。
出題内容
それでは、具体的に出題内容について以下に述べます。
まずおおまかな概要ですが、四肢択一問題が25問、複合式問題(四肢択一のうえ、選択した理由を 100 字以内で記述する問題)が10問出題されます。
覚えている範囲内にはなりますが、四肢択一問題は次のような内容でした。
(※試験終了後、内容を思い出しながら急いで書き起こしたため、細かい部分は相違があるかもしれません。ご了承ください)
・問 以下の事象を、時系列順に並べなさい
- ア 笹子トンネル天井版崩落事故
- イ 国土交通省「道路メンテナンス会議」設立
- ウ 国土交通省「道路橋の予防保全に向けた有職者会議の提言」
- エ 日本構造物診断技術協会発足
・問 伸縮装置の損傷原因として、不適当なものを選びなさい
- 交通量が多く、大型車が多い
- 供用後30年以上経過後、活荷重の繰り返し
- 鋼製フィンガージョイントでは叩き点検が有効で、叩き点検により高い音が返ってきたら疑う
- 忘れました・・
簡単ですが、このような内容でした。
次に複合式問題(記述)については、以下のような問題です。
・問 損傷の評価について、不適当なものはどれか。また、その理由も併せて答えなさい。
- き裂は位置や大きさに関係なくき裂として書く
- ボルトやリベットの破断は「破断」ではなく「ゆるみ・脱落」として扱う
- 板厚減少を伴わない腐食は防食機能の劣化とする
- 耐候性鋼材は・・(忘れました)
このような内容でした。
最後に、断片的に覚えているキーワードだけ簡単に列記しておきます。
・NDT技術者について
・サーモグラフィ法、超音波法
・腐食しやすい箇所(桁端部、添接部、格点部)について
・化学的腐食、塩害、ASRについて
・中性化の計算問題
・鉄道橋の評価区分について
・床板の強度について
・VT、UT、PT、ETについて
・点検の種類(中間点検、定期点検等)
・評価に用いる荷重について(A活荷重、B活荷重など)
・ボルトの遅れ破壊について(記述)
・トフド法について(記述)
・補修工法について(記述)
以上になります。
見てわかるように、非常に幅広く、まんべんなく出題されます。
できる限り早めに対策しておくのがよさそうです。
また、試験管の方から記述問題に関するアドバイスを頂いたのですが、
「もし答えがわからなくても何かしら解答欄を埋めてください」とのことでした。
とにかく埋める、ということを強めに話されていたので、キーワードになり得るものを入れておくと部分点につながるかもしれません。(的外れなキーワードだと減点されるかもしれないので、そこは注意してください)
最後に
それでは最後に、今回のポイントをまとめておきます。
・勉強方法はインプットとアウトプットの繰り返し
・講習会には参加しなくても合格はできる
・コンクリート診断士と土木鋼構造診断士の問題集が参考になる
・記述問題はとにかく埋める
・構造物診断士の過去問題集はない
・問題用紙は持って帰れない
今回は以上になります。少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。